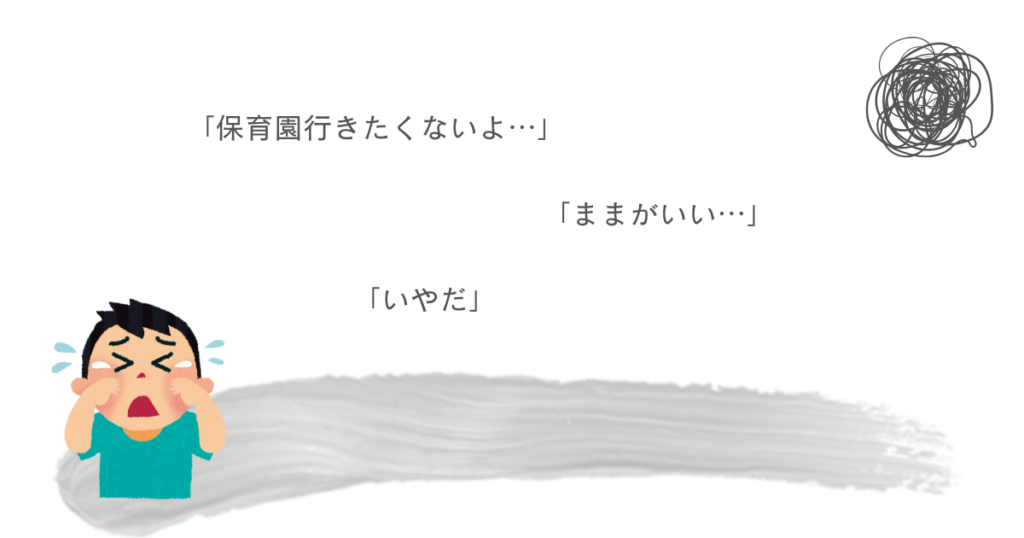
お盆休みや年末年始、ゴールデンウィークなどの長期休暇明け。
朝になると——「保育園行きたくない!」 「ママと一緒がいい…」そんな言葉と涙に、戸惑った経験はありませんか?
服を着ない、玄関から動かない、泣いてしがみつく……。
毎朝これが続くと、親の心も体もすり減ってしまいますよね。
でも安心してください。
長期休み明けの登園しぶりは、多くの家庭で起こる“一時的で自然な反応”です。
私は保育園で働く看護師として、毎年この時期にたくさんの親子を見てきました。
泣いていた子が、数日〜数週間で自然と笑顔を取り戻す姿も何度も経験しています。
この記事では、
- なぜ長期休み明けに登園しぶりが起こるのか
- 親子の負担を減らし、笑顔で登園しやすくなる具体的な工夫
- やってしまいがちなNG対応とその代替案
を、保育園看護師+母親の視点でわかりやすく解説します。
 まいこ@保育園看護師まま
まいこ@保育園看護師まま「今まさに悩んでいる」という方も、 「次の長期休みに備えたい」という方も、 ぜひ参考にしてください。
この記事でわかること
- 長期休み明けに登園しぶりが起こる理由(発達・心理の視点)
- 泣く子が笑顔になりやすい5つの具体的な工夫
- 登園しぶりを悪化させやすいNG対応と正しい関わり方
- 休み明けをラクにする生活リズムの整え方
なぜ長期休暇明けに登園しぶりが起こるのか
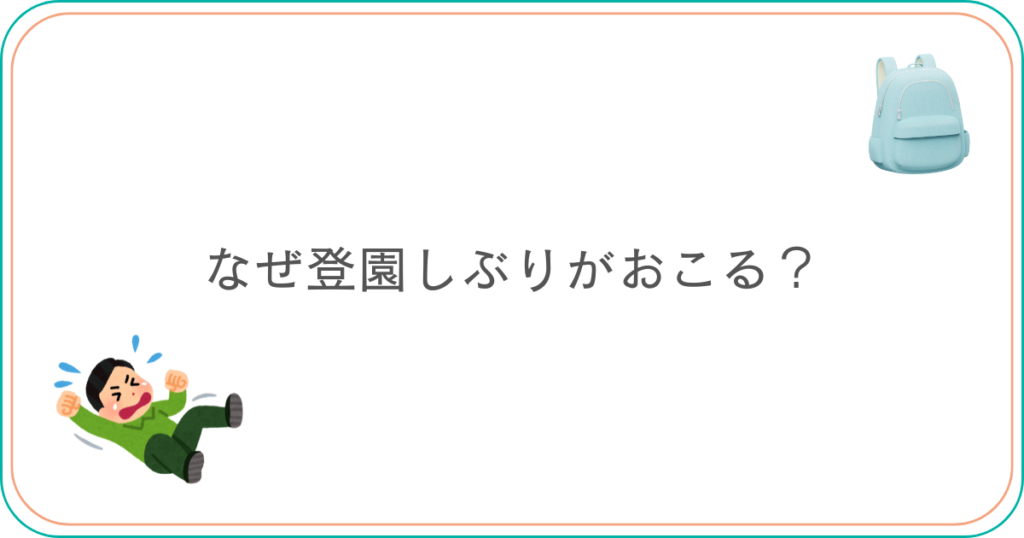
長期休み明けの登園しぶりは、わがままでも甘えすぎでもありません。
子どもの心と体が、再び集団生活に適応しようとする過程で起こる自然な反応です。
1. 生活リズムの乱れによる心身の負担
休暇中は、
- 寝る時間が遅くなる
- 起きる時間が不規則になる
- 昼寝が増える
など、どうしても生活リズムが崩れがちです。
体内時計が乱れると、
- 朝スイッチが入らない
- だるい・眠い
- 気持ちの切り替えが難しい
といった状態になりやすく、登園への抵抗感が強くなります。
2. 家族と離れる不安(分離不安の一時的な再燃)
長期休暇中は、親や家族と過ごす時間が一気に増えます。
この安心できる環境から離れることは、特に2〜5歳の子どもにとって大きな不安です。
成長過程で自然にみられる「分離不安」が、休み明けに一時的に強く出ることがあります。
3. 集団生活への再適応の負荷
保育園では、
- ルールを守る
- 順番を待つ
- 友達と関わる
など、家ではあまり使わないエネルギーを使います。
休み明けは、それを思い出して実行するだけでも負担になります。
4. 甘えの再強化
休み中にたっぷり甘えられたことで、 「もっと一緒にいたい」という気持ちが強くなるのも自然な反応です。
特に、
- 年少児
- 入園・進級して間もない子
は登園しぶりが出やすくなります。
5. 環境変化への戸惑い
- クラス替え
- 担任の先生の変更
- 保育室の配置換え
などの変化も、子どもにとっては大きなストレス要因です。
6. 成長による感受性の変化
休暇中の心身の成長により、 以前は平気だった刺激に敏感になることもあります。
これは成長の証でもありますが、一時的に登園しぶりとして表れることがあります。
泣く子が笑顔になる5つの工夫
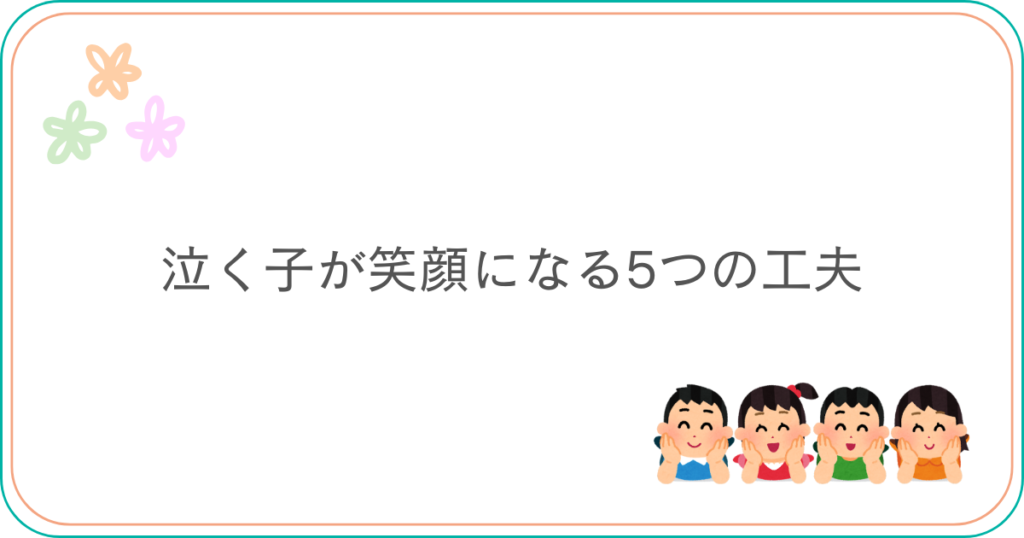
1. 朝の準備を「遊び」に変える
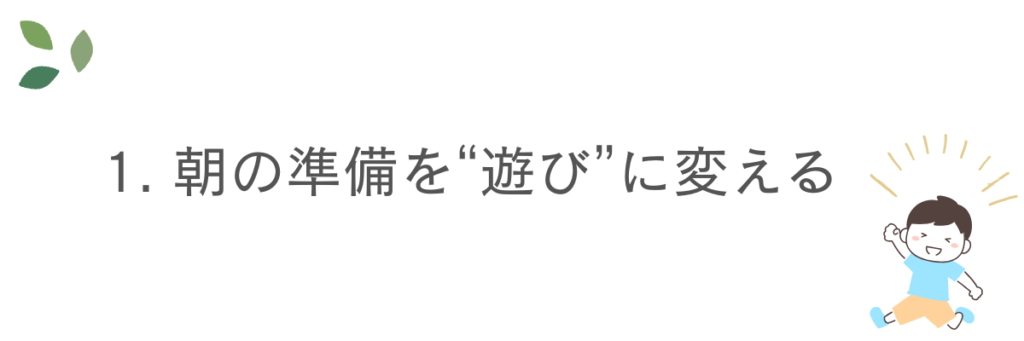
- タイマーを使ったチャレンジゲーム
- 「どっちが早く靴下履けるかな?」と声かけ
- できたらハイタッチやシール
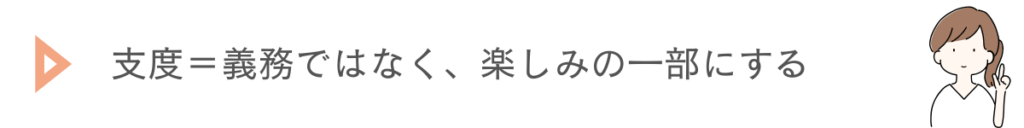
 まいこ@保育園看護師まま
まいこ@保育園看護師まま遊び要素を入れることで、やる気を引き出しやすくなります。
2. 保育園での楽しみを事前に伝える
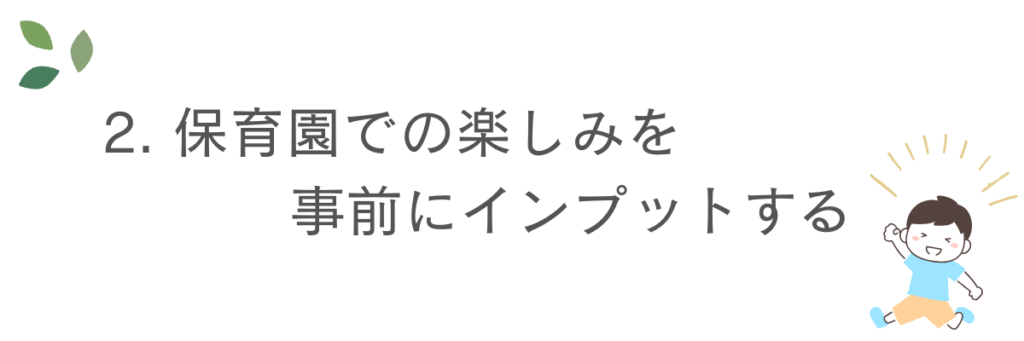
- 「今日は○○ちゃんと遊べるね」
- 「先生にお休みの話しようね」
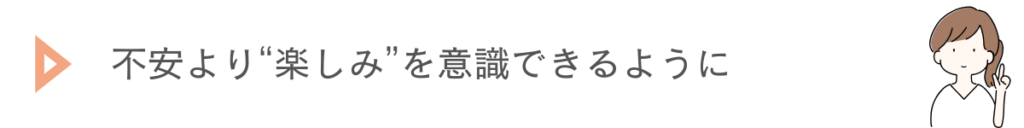
 まいこ@保育園看護師まま
まいこ@保育園看護師まま楽しい予測は不安を和らげる効果があります。
3. スキンシップで安心感をチャージ
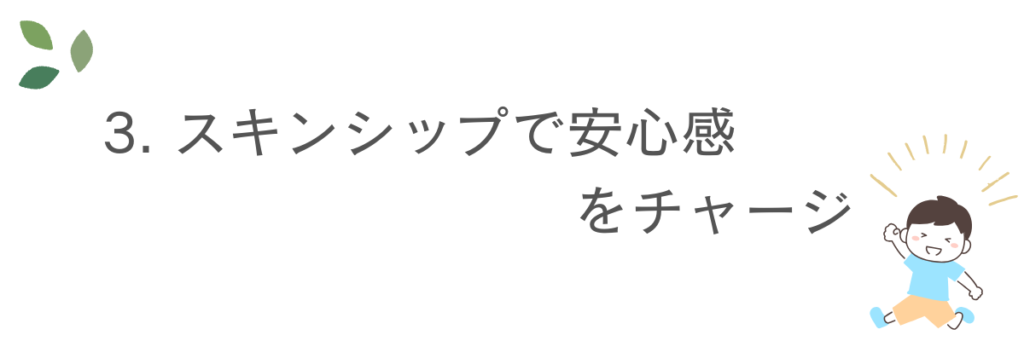
- 玄関でぎゅっと抱きしめる
- 「帰ったら○○しようね」と約束する
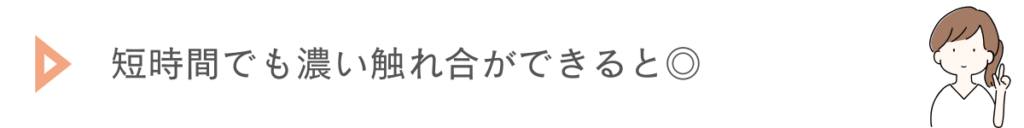
 まいこ@保育園看護師まま
まいこ@保育園看護師まま肌の触れ合いは安心感を高めます。
4. 親ができるだけ落ち着いて送り出す
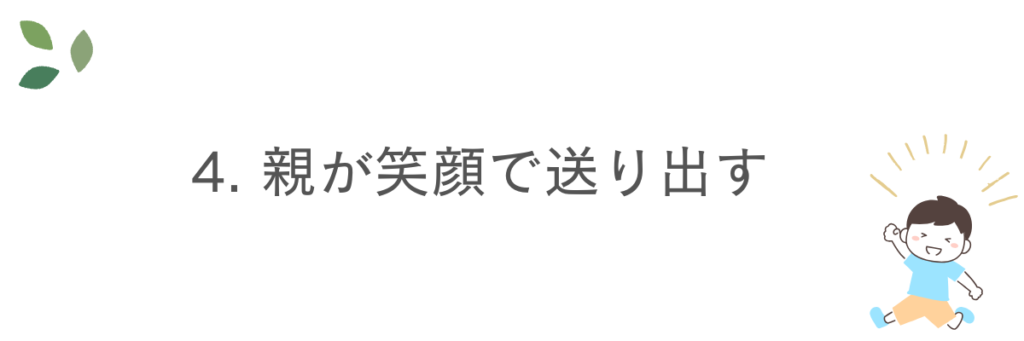
- 笑顔を意識する
- お別れは短く区切る
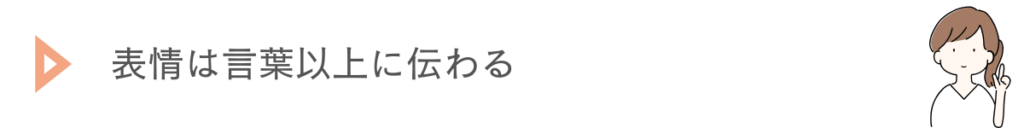
 まいこ@保育園看護師まま
まいこ@保育園看護師まま親の表情は子どもに強く影響します。
5. 前日の準備で朝の余裕を作る
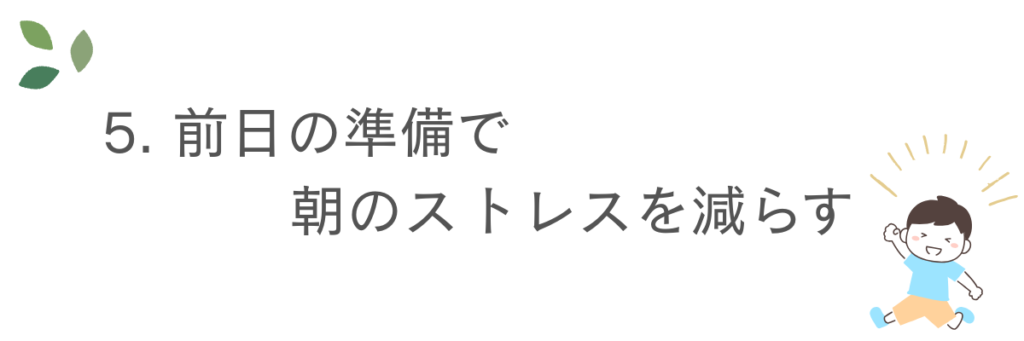
- 服・持ち物をセット
- 朝食を簡単に決めておく
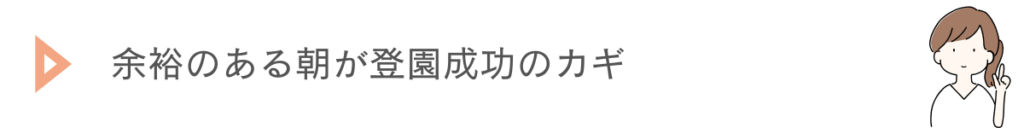
 まいこ@保育園看護師まま
まいこ@保育園看護師まま朝の余裕は、子どもの安心につながります。
登園しぶりのときに避けたいNG対応

- 無理やり引き離す
- 長すぎるお別れ
- 脅すような言葉かけ
- 気持ちを否定する言葉
- 親の焦りをそのまま出す
- 安易に休ませ続ける
代わりに、 「気持ちを受け止めて、短く・安心できる関わり」を意識しましょう。
予防のためにできる生活リズムの戻し方
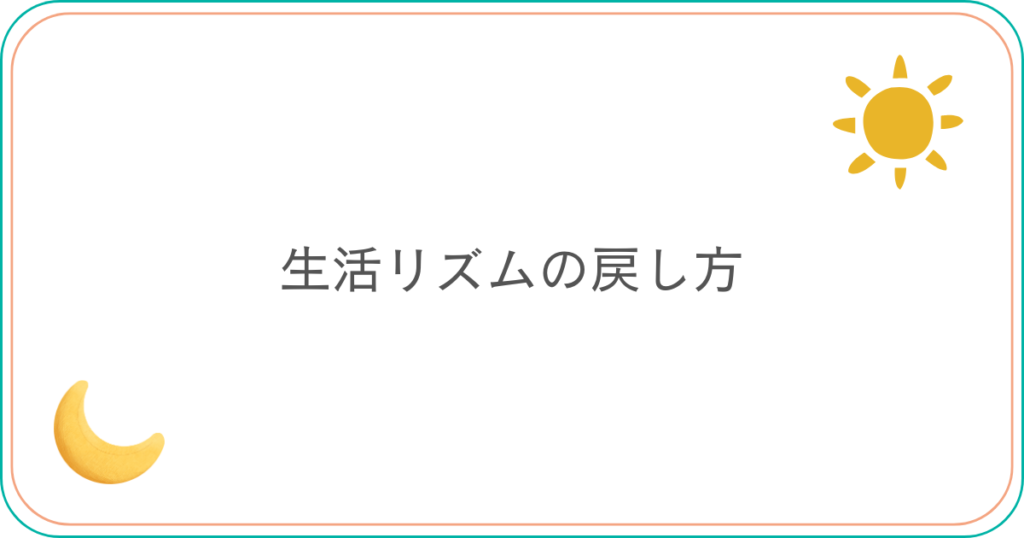
1. 休み終盤から“登園時間仕様”に戻す
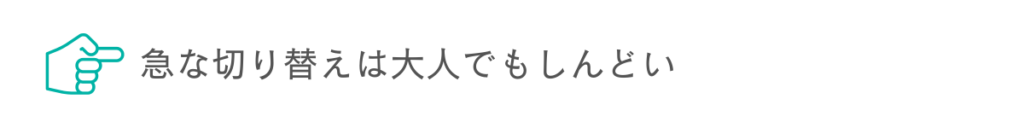
- 長期休暇の3〜4日前から、起床・朝食・就寝時間を登園時と同じようしてみる
- 休日モードで昼寝や夜更かしが続くと、朝の目覚めがつらくなり、ぐずりやすくなる
→10〜15分ずつ時間を早めていくと、体内時計の負担が少なくてすむ
2. 朝の“登園準備ルーティン”を復活させる
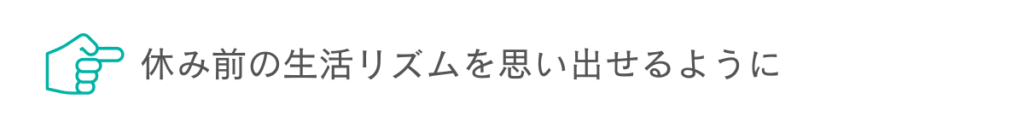
- 保育園バッグを出す、着替えを自分で選ぶ、靴を揃えるなど
- 前日夜から「明日も保育園ごっこしようか」と遊びの延長で準備させる
→行動のパターン化は安心感を生み、登園しぶり予防になる
3. “保育園っぽい”過ごし方を意識する
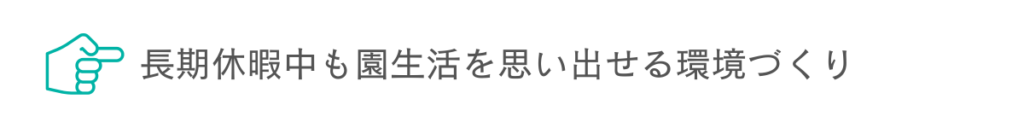
- 昼食やおやつの時間を園と同じぐらいの時間にしてみる
- 園でよく遊ぶおもちゃや歌、絵本を家で取り入れる
- 可能であれば園のお友達や先生と交流する
→記憶の橋渡し効果で、園生活への再適応がスムーズとなる
4. 身体をしっかり動かす時間を作る
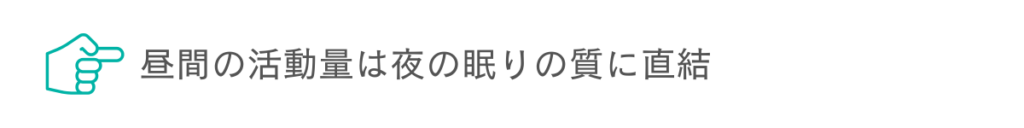
- 午前中に公園遊びやお散歩で太陽光を浴びる
- 室内ならダンスやストレッチで体を温める
→太陽光は体内時計をリセットし、夜のメラトニン分泌を促して入眠しやすくなる
5. 親子で休み明けの話題をポジティブにする
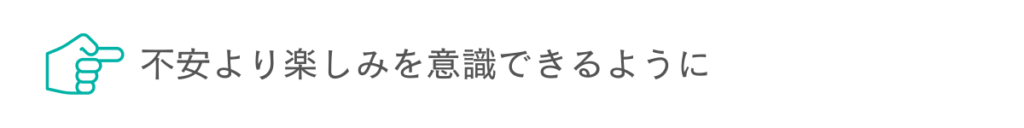
- 「○○ちゃんと遊べるね」「先生に休み中のお話ししようね」とワクワクする話をする
- 「ママもお仕事で新しいことがあるよ」と、自分も切り替えている姿を見せる
→親子で“切り替えスイッチ”を共有できる
6. 前日は“早寝モード”を徹底
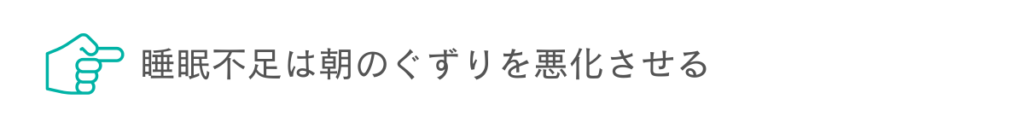
- 夕方以降はテレビ・タブレットの使用を控えて、照明も少し暗めにする
- 寝る前に絵本やマッサージなどリラックスタイムを取り入れる
→ブルーライトや刺激的な遊びはメラトニン分泌を妨げる
この流れを休暇の最終3〜4日間で段階的に取り入れるといいでしょう。
生活リズムを整える過程での工夫について、詳しくまとめています。↓
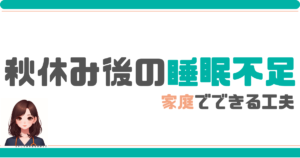
保育園の先生に相談してみる
「家では泣くけど、園に着くとすぐ元気になる」という子も多いです。
先生は毎年たくさんの登園しぶりを見ているので、具体的なアドバイスをもらえます。
家庭と園が連携することで、子どもも安心感を得られます。
まとめ
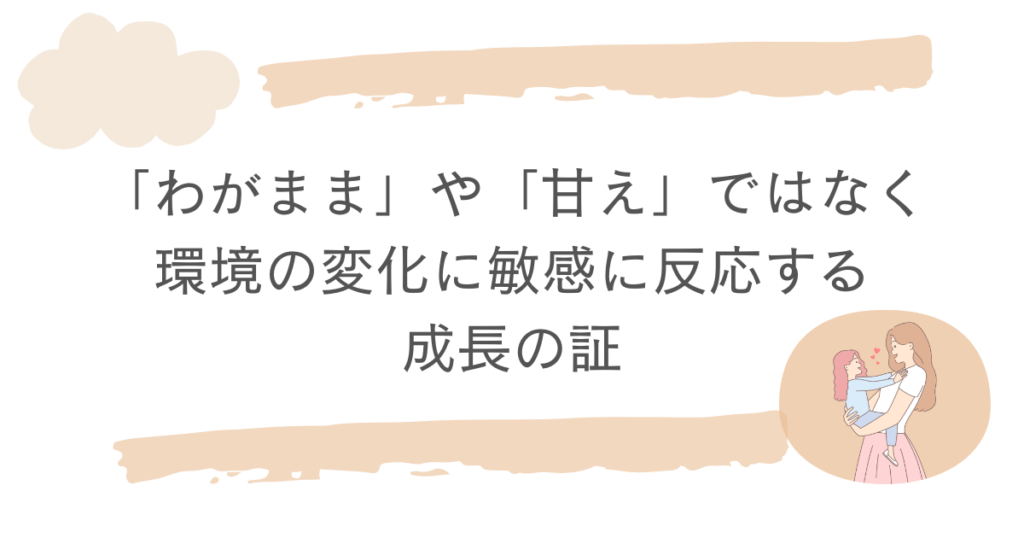
長期休暇明けの登園しぶりは、決して「わがまま」や「甘え」ではなく、環境の変化に敏感に反応する成長の証です。
泣いてしまうのも、行きたくないと言うのも、子どもが自分なりに気持ちを表現しているからこそ。
今回ご紹介した「生活リズムの戻し方」や「笑顔になる5つの工夫」、「避けたいNG対応」を意識すれば、子どもの不安は少しずつ和らぎ、笑顔で登園できる日が増えていきます。
大切なのは、親も子も無理をせず、少しずつ慣らしていくこと。
今日できたことを認め合いながら、休み明けの朝を前向きにスタートできるようサポートしましょう。
そして、泣きながら登園した日でも、迎えに行ったときに笑顔で過ごしていたなら、それは大きな一歩です。
長期休暇明けの登園しぶりは、必ず乗り越えられる壁。
 まいこ@保育園看護師まま
まいこ@保育園看護師まま親子で一緒に、小さな「できた!」を積み重ねていきましょう。


コメント