
 お母さん
お母さん指しゃぶりが辞められないようです。
これって大丈夫かしら・・?
 まいこ@保育園看護師まま
まいこ@保育園看護師まま指しゃぶりが辞められなくて心配しているのですね。
私も看護師として、そしてママとして、息子の“指しゃぶり期”に本当に悩みました。
子どもの気持ち・発達の視点も交えながら指しゃぶりについて、説明していきますね。
赤ちゃんのころから当たり前のようにしていた「指しゃぶり」。
けれど、成長してもなかなかやめられない姿を見て、「歯並びに影響がある?」「心のサインかも?」と心配になるママやパパも多いのではないでしょうか。
私自身も一人の母として悩み、そして看護師として発達や心理面から多くの子どもを見てきました。
この記事では、なぜ指しゃぶりや爪噛みが続くのか、その背景にある子どもの気持ちや発達の視点をていねいに解説します。
あわせて、無理なくやめていくための具体的な対応策や、話題の対策グッズもご紹介。
「やめさせなきゃ」と焦る前に、少しだけ子どもの気持ちに寄り添ってみませんか?
 まいこ@保育園看護師まま
まいこ@保育園看護師ままちょっと専門な視点も交えながら、やさしく、しっかりとサポートしていきますね。
この記事でわかること
- 子どもの指しゃぶり・爪噛みが続く理由と、発達や心理の背景
- 日常でできるやめさせ方(NG対応/対応パターン別)
- 歯並びや口腔への影響と、受診の目安
- 無理なく取り入れられる対策グッズの考え方と選び方
 まいこ@保育園看護師まま
まいこ@保育園看護師まま保育園で多くの子どもを見てきた看護師として、指しゃぶりや爪噛みは「意味がある行動」だと感じています。
指しゃぶり・爪噛みは「心のサイン」
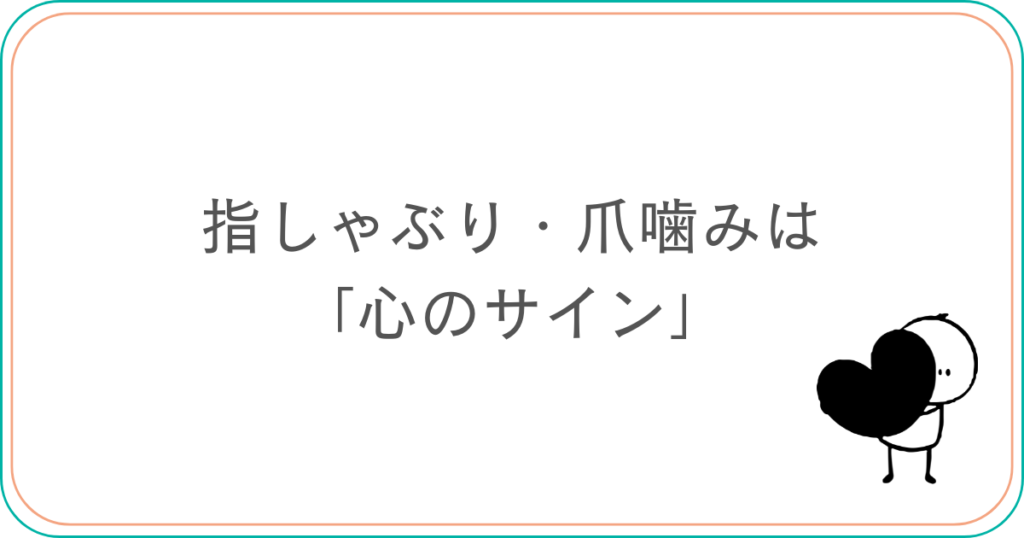
指しゃぶりや爪噛みは、単なるクセではありません。
多くの場合、子どもが自分の気持ちを整えるために行っている行動です。
特に未就学児は、
- 不安
- 緊張
- さみしさ
- 疲れ
といった感情を、言葉でうまく表現することがまだ難しい時期。
その代わりとして、指しゃぶりや爪噛みで自分を落ち着かせていることがあります。
安心したい気持ちのあらわれ
赤ちゃんの頃、指しゃぶりは安心して眠るための大切な行動でした。
成長しても続く場合、それは「まだ安心が必要だよ」という心のサインであることも。
環境の変化(入園・進級・引っ越し・家族構成の変化など)があると、一時的に増えることもよくあります。
「やめられない」のではなく「やめなくていい理由がある」
大人から見ると「もう大きいのに」と感じてしまうこともありますよね。
でも子どもにとっては、
- 落ち着く方法
- 気持ちをリセットする手段
- 不安をやわらげる習慣
として、今は必要な行動なのかもしれません。
無理に取り上げてしまうと、別の形(夜泣き・癇癪・他のクセ)で表れることもあります。
保育園看護師として感じていること
保育園で多くの子どもを見てきて、指しゃぶりや爪噛みが強く出る子ほど、がんばり屋さんなことが多いと感じます。
集団生活の中で一生懸命合わせている分、家や安心できる場所で、気持ちを調整しているのです。
大切なのは「行動」より「気持ち」に目を向けること
指しゃぶり・爪噛みをやめさせる前に、
- 最近、何か変化はなかったかな?
- 無理してがんばっていないかな?
- 安心できる時間は足りているかな?
そんなふうに、子どもの背景に目を向けてみてください。
 まいこ@保育園看護師まま
まいこ@保育園看護師まま行動は、心のメッセージ。気持ちが満たされていくと、行動も自然と変わっていきます。
・指しゃぶり・爪噛みは安心を得るための行動
・無理にやめさせると逆効果
・環境や心の状態を見ることが大切
やめられない理由は「脳」と「環境」にある?
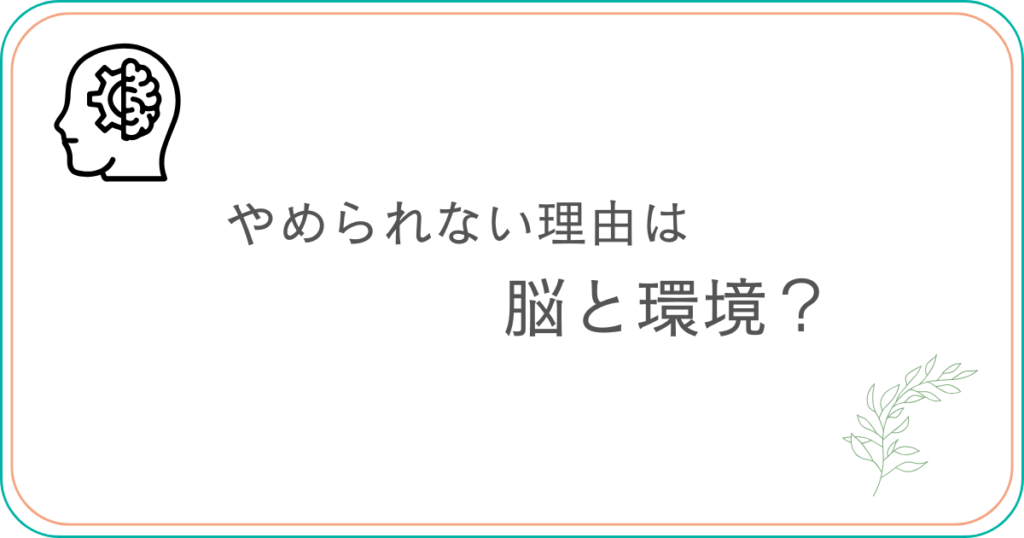
看護師の視点からお伝えすると、
やめられない背景には、以下のような要素が考えられます。
感覚過敏・鈍麻の傾向
子どもによっては、触覚や口腔内の感覚の刺激を求めていることがあります。
これを「感覚統合」の視点で見ると、爪を噛むことで感覚を調整しようとしている場合も。
 まいこ@保育園看護師まま
まいこ@保育園看護師ままこのような場合は、チューブ型おもちゃや咀嚼グッズなどが代替になります。
環境のストレス
家庭や園での変化、不安な出来事(お別れ・引っ越し・ママが仕事復帰したなど)があった際、無意識のうちに口元に手が向かうことがあります。
 まいこ@保育園看護師まま
まいこ@保育園看護師まま本人も気づいていない心の不安を、行動から汲み取ってみましょう。
注意されるほど強化される
「やめなさい」と言われることで、逆に意識してしまい、クセが強くなることも。
 まいこ@保育園看護師まま
まいこ@保育園看護師まま対処よりも環境づくり・寄り添うことが大切です。
指しゃぶり・爪噛みをやめさせるときにNGな対応

指しゃぶりや爪噛みへの対応で、実は逆効果になりやすいのがこちら。
怒る・叱る・無理にやめさせる
指しゃぶりは、子どもにとって「安心感」や「ストレス解消」の手段です。
そこに対して怒ったり叱ったりすると、子どもは不安やストレスをさらに感じ、指しゃぶりが増えてしまう可能性があります。
また、強制的にやめさせることで、自尊心が傷ついたり、他の形で不安を表す行動(爪かみ・夜泣き・おねしょなど)に移ることもあります。
恥ずかしいからやめてと言う
「恥ずかしい」「みんなに笑われるよ」などの声かけは、羞恥心を利用したプレッシャーです。
これは子どもの自己肯定感を傷つける原因になります。
「自分は悪い子なんだ」「ダメなんだ」と感じてしまい、指しゃぶりの原因となっていた不安や緊張がより深まる恐れがあります。
結果的に、指しゃぶりが改善するどころか悪化してしまうことも。
クセを無理にやめることがゴールになる
大切なのは「なぜ指しゃぶりをしているのか」という背景(心理的な安心・環境のストレス)に目を向けることです。
やめさせることだけを目標にすると、子どもの内面の不安や理由に気づけず、根本的な解決につながりません。
行動の「表面」だけを直しても、気持ちのケアがされなければ、別の問題行動として現れる可能性もあります。
保育園看護師ママのおすすめ対策7選
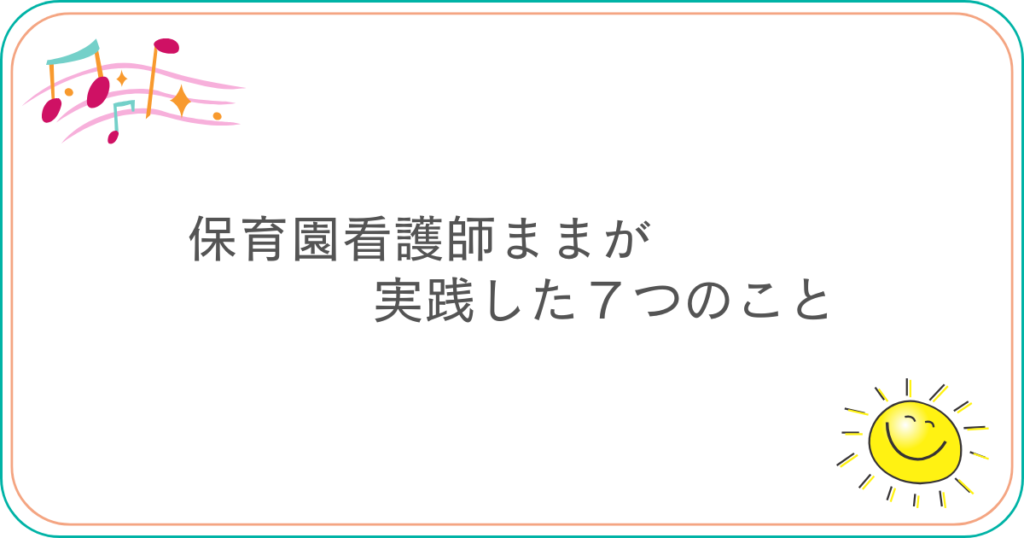
保育園でたくさんの子どもたちを見てきて、そして一人の母として悩んできた経験から感じるのは、
指しゃぶり・爪噛みには「その子なりの理由」が必ずあるということです。
「今すぐやめさせる」よりも、安心を積み重ねる関わりが結果的に近道になります。
① まずは否定せず、そのまま受け止める
「まだしてるの?」ではなく、
「そっか、今は落ち着きたいんだね」と心の中で受け止める。
大人が構えすぎないことで、子どもも安心します。
② 気持ちを代弁する声かけをする
子どもは、自分の気持ちをうまく言葉にできません。
- 「ちょっと不安だったのかな」
- 「今日はがんばったもんね」
そんな一言が、指しゃぶり・爪噛みの回数を減らすきっかけになります。
③ スキンシップの時間を意識的に増やす
抱っこ、手をつなぐ、背中をなでる。
短時間でも、毎日同じタイミングでのスキンシップは、子どもの安心感を大きく高めます。
④ 手を使う遊びで“代わりの行動”を用意する
指しゃぶり・爪噛みは「手持ち無沙汰」でも起こりやすい行動。
- 粘土・折り紙・ブロック
- ボール遊びやお絵かき
手が自然に使われる遊びを増やすことで、行動がゆるやかに置き換わっていきます。
⑤ 寝る前の安心ルーティンを作る
寝る前は、不安が出やすい時間帯。
- 絵本を読む
- 同じ子守唄を歌う
- 「今日も大好きだよ」と伝える
毎晩同じ流れをくり返すことで、指しゃぶりに頼らなくても眠れるようになる子も多いです。
⑥ 年齢や状況に応じて対策グッズを補助的に使う
年齢が上がっても続く場合は、
“本人の納得ありき”で対策グッズを使うのも一つ。
- 指しゃぶり防止マニキュア
- 寝るとき用の指カバー
- 爪噛み防止コート
「やめさせるため」ではなく、「一緒にがんばるサポート」として使うのがポイントです。
⑦ 必要なら専門家に相談する
- 5〜6歳以降も強く続いている
- 出血・炎症・歯並びへの影響が出ている
- 不安がとても強そうに見える
そんなときは、歯科・小児科・発達相談などに相談してOK。
早めの相談=悪いことではありません。
保育園看護師ママからのメッセージ
焦らず、責めず、少しずつ安心を重ねていけば、子どもは自分のタイミングで手放していきます。
 まいこ@保育園看護師まま
まいこ@保育園看護師ままママやパパも、ひとりで抱え込まなくて大丈夫ですよ。
指しゃぶり・爪噛みの影響と、受診を考える目安
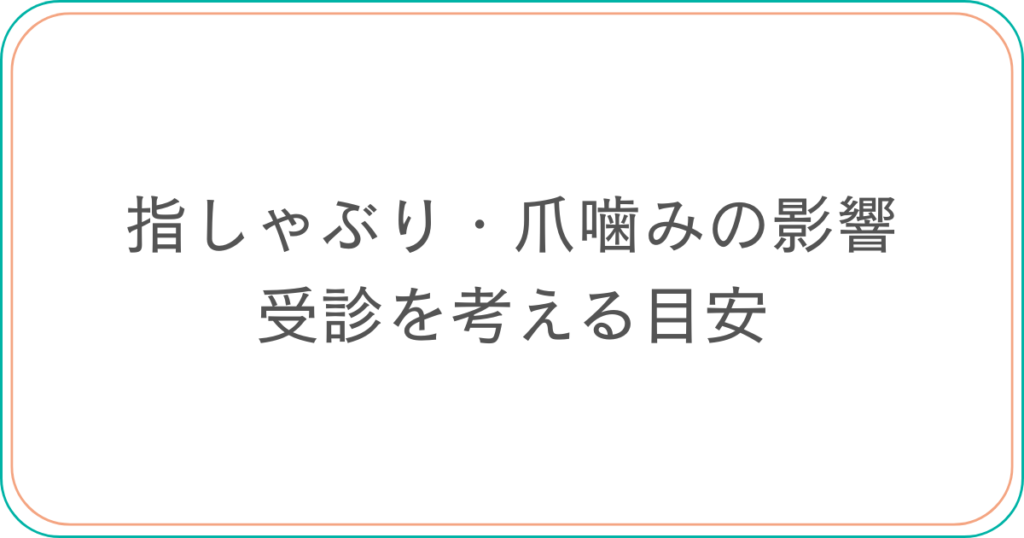
指しゃぶりや爪噛みは、すぐに「悪い癖」「やめさせなきゃ」と思われがちですが、年齢や頻度によって影響の出方は大きく異なります。
ここでは、保護者が気になりやすい影響と、「受診を考える目安」を整理してお伝えします。
歯並び・口の中への影響
長期間・頻繁に指しゃぶりが続くと、歯やあごに影響が出ることがあります。
- 前歯が前に出てくる
- 上下の歯がかみ合わない(開咬)
- 舌の位置が安定しにくい
ただし、乳歯の時期(〜3歳頃)までの指しゃぶりは、自然に減っていくことも多く、必ずしも問題になるわけではありません。
歯並びへの影響が心配になるのは、4〜5歳以降も日中・就寝中ともに強く続いている場合です。
皮膚・爪への影響
爪噛みや指しゃぶりが強い場合、以下のようなトラブルが見られることがあります。
- 指先が赤く腫れる、ひび割れる
- ささくれや出血が増える
- 爪が変形したり、深爪になる
- ばい菌が入って炎症を起こす
痛みや傷があると、逆に不安が強まり、癖が強化されてしまうこともあります。
皮膚トラブルが続く場合は、早めにケアや相談を検討してもよいでしょう。
心への影響はある?
指しゃぶりや爪噛みそのものが、直接「心の問題」につながるわけではありません。
ただし、
- 強い不安や緊張が長く続いている
- 環境の変化(入園・進級・引っ越しなど)のあとに急に増えた
- 他にも癇癪・睡眠トラブルが目立つ
こうした場合は、子どもが気持ちをうまく表現できず、癖として出ているサインの可能性があります。
受診を考える目安
以下に当てはまる場合は、一人で抱え込まず、専門家に相談してみましょう。
歯科への相談を考える目安
- 4〜5歳を過ぎても強い指しゃぶりが続いている
- 歯並びやかみ合わせが明らかに気になる
- 定期健診で指摘を受けた
小児科・保健センター・発達相談の目安
- 癖が急に強くなった
- 生活や睡眠に支障が出ている
- 不安やストレスが強そうで心配
相談することは、「やめさせるため」ではなく、今の子どもの状態を知るための大切な手段です。
「様子見」で大丈夫なケースも多い
- 年齢が低い
- 寝る前や安心したときだけしている
- 少しずつ頻度が減ってきている
こうした場合は、無理にやめさせようとせず、見守りながら関わることで自然と落ち着くことも多いです。
指しゃぶり・爪噛みは、「困った癖」ではなく、子どもなりに気持ちを整えようとしているサイン。
 まいこ@保育園看護師まま
まいこ@保育園看護師まま心配なときは、ひとりで抱えず、頼れる場所を上手に使いながら、子どものペースを大切にしていきましょう。
クセの奥には「理由」がある
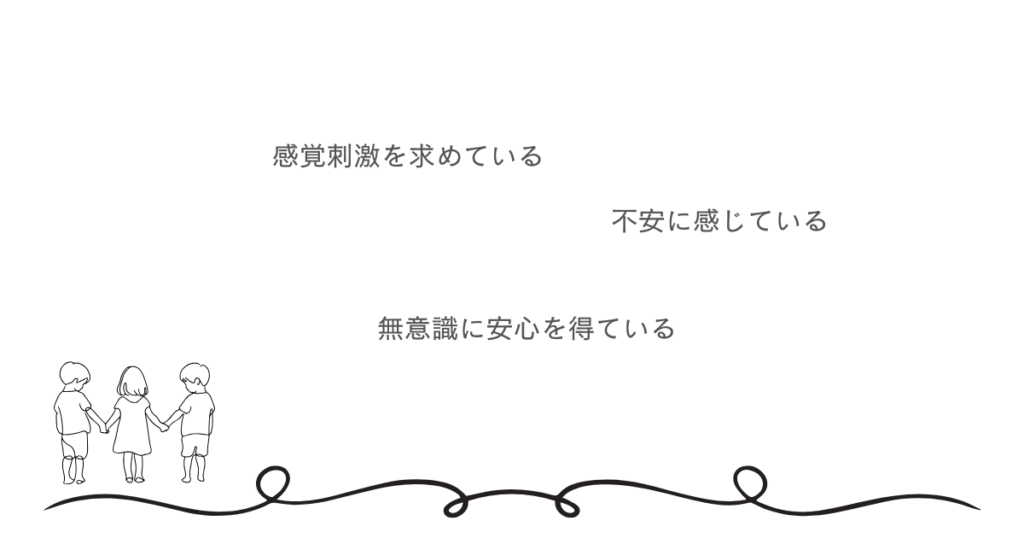
指しゃぶりや爪噛みを見ていると、「どうしてやめられないの?」と感じてしまいますよね。
でも、これらの行動の奥には、必ず子どもなりの理由があります。
子どもはまだ、自分の気持ちを言葉で整理したり、大人のように感情をコントロールすることができません。
その代わりに、
- 指を口に入れる
- 爪を噛む
- 同じ動きをくり返す
といった行動を通して、心のバランスを取ろうとしているのです。
不安・緊張・疲れを感じているサイン
保育園や幼稚園、習い事など、子どもは毎日たくさんの刺激を受けています。
集団生活の中で
- がんばっている
- 気をつかっている
- 緊張している
そんな状態が続くと、家でふっと力が抜けた瞬間にクセが出やすくなります。
それは「甘えている」のではなく、安心できる場所で本音が出ている状態とも言えます。
「注意されるほど増える」こともある
「やめなさい」「汚いよ」「またやってる」
こうした声かけは、子どもを不安にさせ、クセを強めてしまうことがあります。
子どもにとっては「やめなきゃ」「怒られる」
という気持ちが増え、かえって指しゃぶりや爪噛みが心の逃げ場になってしまうのです。
行動を消すより、安心を増やす
クセをなくすことよりも大切なのは、その行動が必要なくなるくらい、心が満たされること。
- ぎゅっと抱きしめる
- 話をゆっくり聞く
- 一緒に過ごす時間を意識的につくる
そんな関わりが増えていくと、子どもは少しずつ別の方法で気持ちを整えられるようになります。
クセは「成長途中のサイン」
指しゃぶりや爪噛みは、心が弱いから起きるものではありません。
むしろ、「自分なりに気持ちを整えようとしている」「成長の途中で揺れている」そんなサインです。
 まいこ@保育園看護師まま
まいこ@保育園看護師まま焦らず、責めず、「今は必要なんだな」と受け止めてあげることが、結果的にいちばんの近道になります。
どうしても気になるときは「補助的なアイテム」も選択肢に
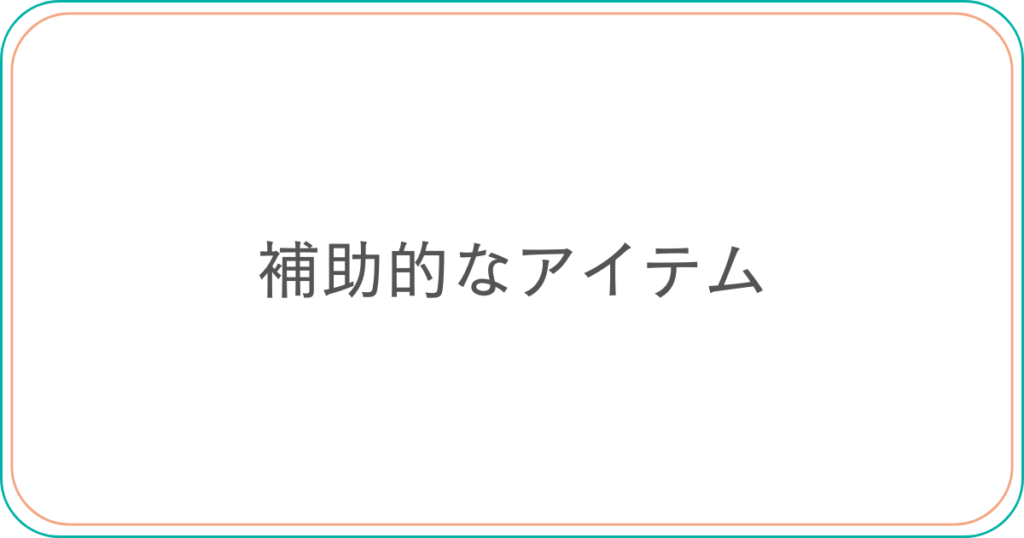
ここまでお伝えしてきたように、指しゃぶり・爪噛みは「無理にやめさせるもの」ではありません。
それでも、
- 本人が「やめたい」と言っている
- 年齢が上がり、歯や皮膚への影響が気になってきた
- 声かけや関わりだけでは難しそう
そんなときは、「叱らずにサポートできるアイテム」を一時的に使うのもひとつの方法です。
我が家でも検討したのが、苦味で気づきを促すタイプの【かむピタ】でした。
無理に我慢させるのではなく、「自分で気づいてやめる」きっかけになる点が、看護師としても安心できるポイントです。
▶ 指しゃぶり・爪噛み対策【かむピタ】の詳細はこちら
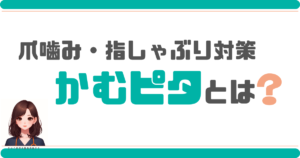
「やめさせなきゃ」と思うほど、親も子も苦しくなってしまうことがあります。
かむピタは、無理にやめさせるのではなく、安心しながら“少しずつ手放す”ためのサポートアイテム。
気になる方は、実際の使い方や口コミをチェックしてみてください。↓

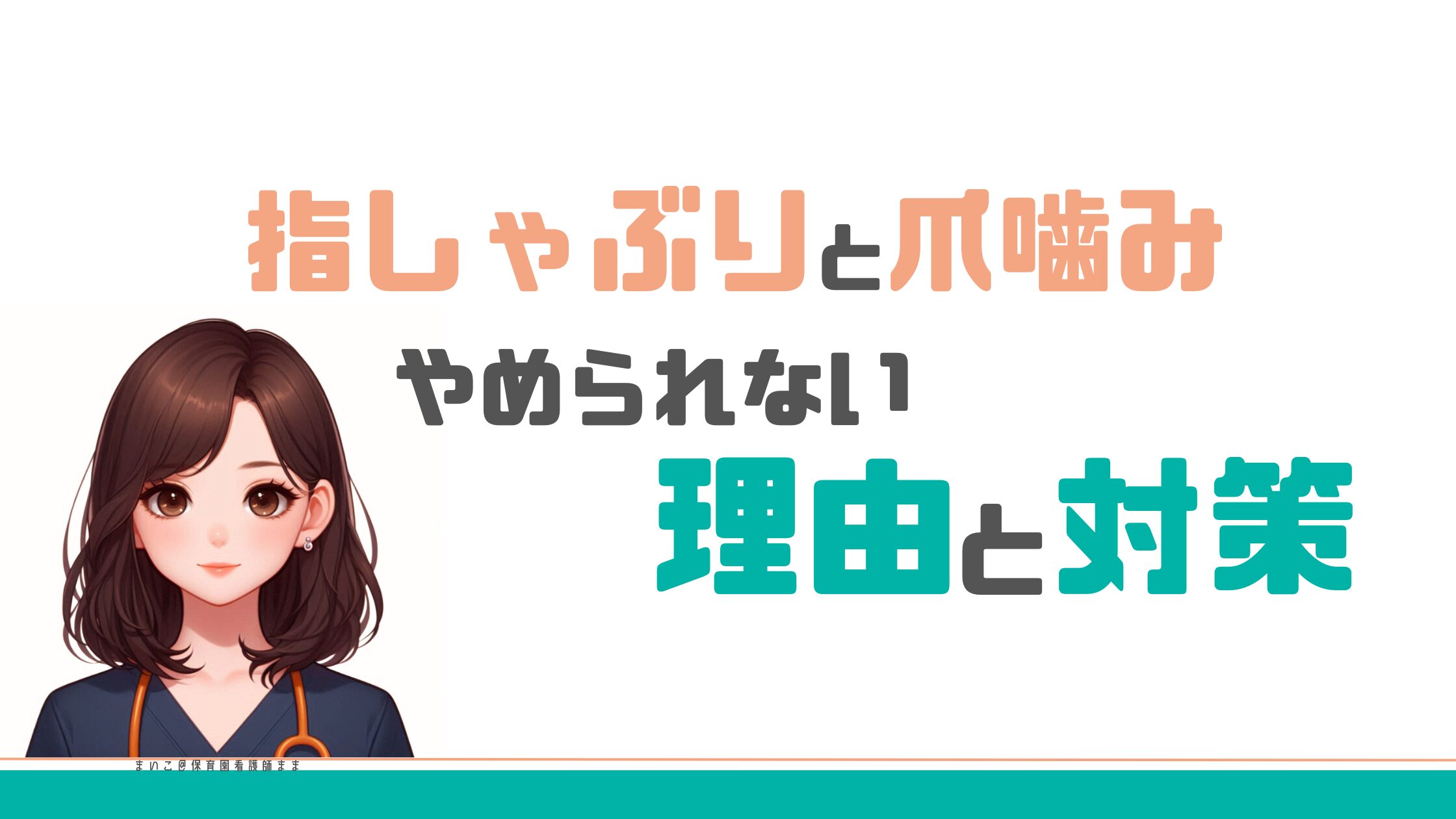
コメント