はじめに

秋休みや連休が明けたあと、「夜なかなか寝てくれない」「朝起きるのがつらそう」そんな子どもの変化を感じていませんか?
実は、秋休み後は子どもの睡眠リズムが乱れやすい時期です。
夜更かしや朝寝坊が続くことで、睡眠不足になり、
- 朝の支度に時間がかかる
- 登園・登校を嫌がる
- 日中ぼんやりして集中できない
といった影響が出ることもあります。
私は保育園で働く看護師として、長期休み明けに体調や情緒が不安定になる子どもたちを多く見てきました。
睡眠リズムの乱れは、体調だけでなく「心の不調」にもつながりやすいため、早めの立て直しが大切です。
 まいこ@保育園看護師まま
まいこ@保育園看護師ままこの記事では、秋休み後に増えやすい子どもの睡眠不足の原因と、家庭で無理なく生活リズムを整える具体的な工夫を、保育園看護師の視点でわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 秋休み後に子どもの睡眠不足が起こりやすい理由
- 睡眠不足が子どもの体調・行動に与える影響
- 生活リズムを整えるために家庭でできる具体的な工夫
- 登園・登校をスムーズにするための親の関わり方
なぜ秋休み後に子どもの睡眠不足が増えるのか
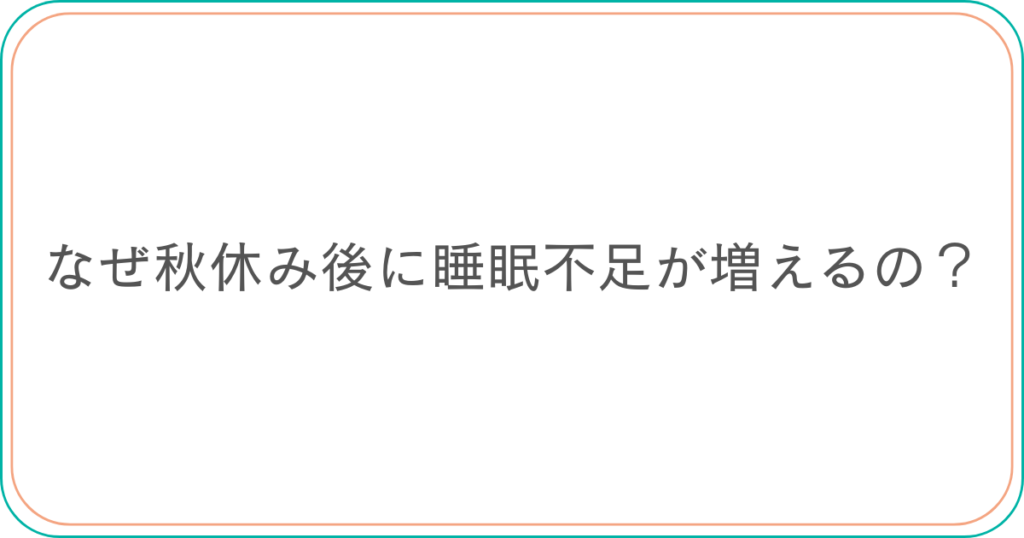
1. 夜更かし・朝寝坊の習慣
秋休みは短いですが、たった2〜3日でも夜更かしと朝寝坊を繰り返すと体内時計はすぐに後ろ倒しになります。
国立精神・神経医療研究センターの報告では、睡眠リズムは「わずか3日」でも簡単にずれるとされています。
小学2年の息子が秋休みに祖父母宅に泊まりに行ったとき、夜11時過ぎまで従兄弟と遊んでいました。
たった2泊でしたが、休み明けは朝起きられず、学校に送り出すまでにいつもの倍の時間がかかりました。
2. 学校行事での疲れが残っている
運動会や遠足、文化祭など、秋は大きな行事が目白押しです。
子どもにとって楽しい体験である一方で、心身に負担がかかります。
疲れが回復しきらないうちに休みモードに入り、さらに夜更かしをすると、リズムが乱れたまま学校が再開することになります。
3. スクリーンタイムの増加
「休みだからいいよね」とつい長時間のゲームや動画視聴を許してしまうご家庭も多いでしょう。
ブルーライトは睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制することが分かっており(Harvard Medical School, 2012)、寝つきの遅れにつながります。
4. 宿題・習い事による夜型化
特に小学校高学年では「休みの課題をまとめてやる」「塾や習い事が夜に入る」ことで、寝る時間がずれ込みやすい傾向があります。
睡眠不足が子どもに与える影響(体調・情緒・行動)
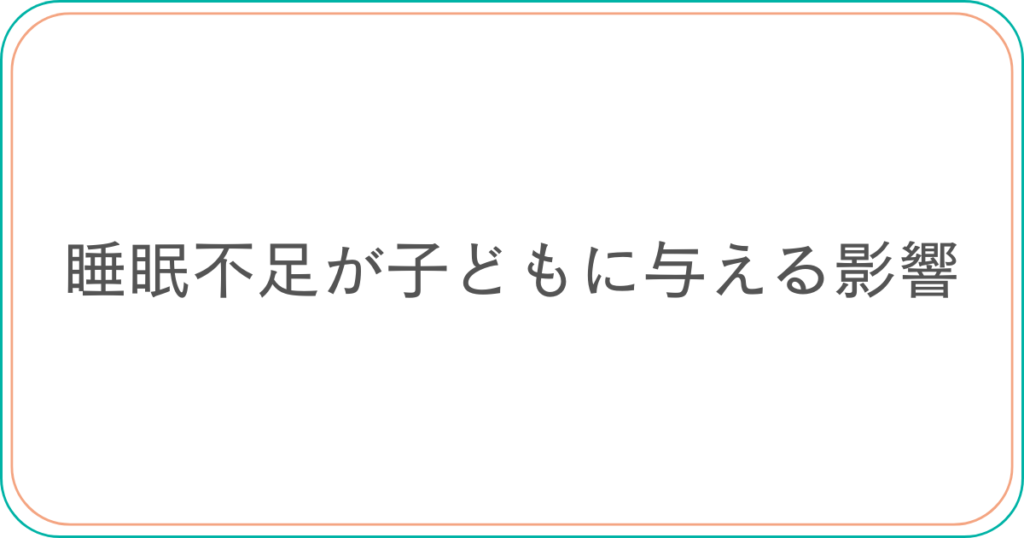
子どもにとって睡眠は「休息」以上の意味を持ちます。
心身の発達を支える“基盤”であり、学習・感情・体調・成長といったすべてに関わっています。
1. 学習効率・集中力の低下
東京大学と国立成育医療研究センターの共同研究(2020)では、小学生約3,000人を対象に調査が行われました。
その結果、睡眠時間が短い子ほど算数や国語の成績が低下する傾向が確認されています。
特に 22時以降に就寝する子は、21時前に就寝する子より平均点が低い ことが分かりました。
これは「睡眠中に脳が記憶を整理・定着させる」ためです。
授業や塾で学んだこと、日中の体験は睡眠中に脳内で整理され、必要な情報として保存されます。
睡眠不足だと、この「情報の仕分け作業」が不十分になり、せっかく学んだことが身につきにくくなってしまうのです。
2. 情緒の不安定化
米国小児科学会(AAP)のガイドラインでは、睡眠不足が子どもの 「衝動性」「怒りっぽさ」「気分の落ち込み」 を増大させると報告されています。
これは、睡眠が感情のコントロールを担う脳の前頭前野や扁桃体に深く関係しているためです。
睡眠が足りないと、ちょっとした刺激に過敏に反応したり、イライラが爆発しやすくなります。
秋休み明けのある朝、息子が「靴下を履きたくない!」と大泣きしたことがありました。
普段なら少し声をかければ気持ちを切り替えられるのに、その日は泣き続け、登校も遅れぎみに…。
あとで振り返ると、前夜にYouTubeを遅くまで見てしまい、睡眠時間が1時間短かったことが原因でした。
「ただのわがまま」ではなく「睡眠不足による情緒の乱れ」だったのだと気づき、私自身の声かけや生活管理の大切さを実感しました。
3. 体調不良・免疫力低下
睡眠不足は、風邪や感染症への抵抗力も下げてしまいます。
Cohenら(2009)の研究によると、睡眠が7時間未満の人は8時間以上眠った人に比べて 約3倍も風邪にかかりやすい という結果が出ています。
これは、睡眠が白血球の働きを高め、ウイルスや細菌に対抗する免疫機能を整える役割を持つためです。
秋から冬にかけて風邪やインフルエンザが流行する時期に、睡眠不足が続くと感染リスクがさらに高まります。
去年の秋休み明け、息子は生活リズムが崩れて夜更かしが続いた後、立て続けに風邪をひきました。
予防接種をしていても、睡眠不足で免疫が落ちていると体調を崩しやすいのだと痛感しました。
4. 成長ホルモン分泌への影響
成長ホルモンは「眠り始めの深いノンレム睡眠時」に最も多く分泌されます。
このホルモンは、背の伸びや筋肉の発達だけでなく、日中の疲労回復や細胞修復にも関与しています。
寝不足が続くと、この大切な成長ホルモンの分泌が不十分になり、 身長の伸びがゆるやかになる・運動後の疲れが取れにくい・肌荒れしやすい といった影響が出る可能性があります。
息子は背の伸びをとても気にしているのですが、睡眠が乱れていた時期は「最近背が伸びてない」と本人も不安そうにしていました。
成長期の子どもにとって「しっかり眠ること」は、栄養や運動と同じくらい大切なことだと実感しています。
睡眠不足が続くと、朝の支度が進まず、登園や登校を嫌がるようになることもあります。
生活リズムの乱れが原因の「行きしぶり」への具体的な対応については、こちらの記事で詳しくまとめています。

秋休み後に生活リズムを整える家庭での工夫
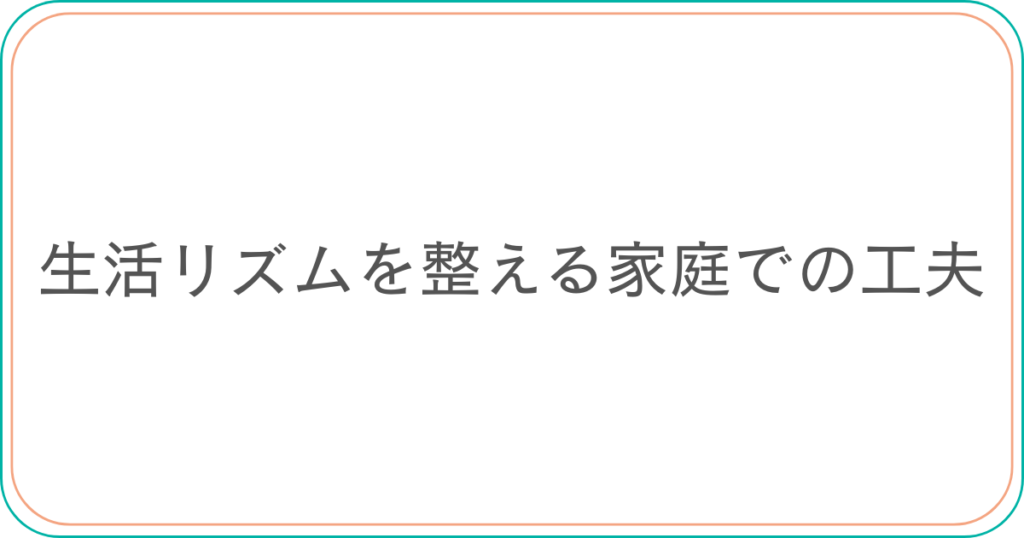
朝の光で体内時計をリセット
人の体は「光」によって体内時計を調整しています。
特に朝の太陽光は、眠気を誘うホルモン「メラトニン」を抑え、代わりに活動スイッチとなる「セロトニン」を分泌させます。
- 起床後はまずカーテンを開け、自然光を浴びる
- 天気が悪い日も、できるだけ外に出て空気を吸う
- 朝食を食べながら日差しを感じられる場所に座る
こうした小さな工夫で、体内時計がリセットされ、夜の眠気も自然と訪れやすくなります。
就寝前のルーティンを整える
眠る前の過ごし方はとても大切です。
脳と体に「そろそろ眠る時間だ」とサインを送る習慣をつくることで、スムーズに入眠できます。
- 寝る1時間前にはゲーム・スマホ・テレビをオフ
ブルーライトは脳を覚醒させるため、眠気が遠のきます。 - 入浴は就寝の1〜2時間前に
一度上がった体温が下がるときに眠気が強まります。 - 寝る前の習慣を固定する
「絵本を読む」「ハーブティーを飲む」「アロマをたく」など。
毎日同じ行動を繰り返すと、脳が「これをしたら眠る」と学習します。
わが家では「歯磨き → 絵本2冊 → 電気を暗くする」という流れを固定しました。
最初は「まだ寝たくない!」と反抗していた息子も、繰り返すうちに自然と眠気が訪れるようになりました。
夕方の軽い運動
日中の活動量が不足すると、夜になっても体が疲れておらず眠れない原因になります。
特に秋は日が短くなり、外遊びの時間が減りがちです。
- 学校や園から帰宅後に20〜30分、外で体を動かす
- 軽い散歩、自転車、ボール遊びなど、激しすぎない運動がおすすめ
- 夕方以降に運動するときは、寝る2時間前までに切り上げる
近所のママ友は秋休み後の数日間「夕方に必ず30分の自転車散歩」を取り入れたそうです。
すると夜は自然と9時前に眠くなり、朝の機嫌も改善。
本人も「朝スッキリ起きられるようになった」と話していたそうです。
休日も起床時間は一定に
休日の「寝だめ」は気持ちよいものですが、子どもの体内時計にとってはリズムを乱す原因になります。
- 平日と休日の起床時間の差は1時間以内に抑える
- 「休みの日でも朝ごはんは同じ時間に食べる」ことを意識する
- 午後に強い眠気が出たら、20〜30分の昼寝で調整するのがおすすめ
以前お昼寝の時間が遅くなったとき、夜11時になっても眠れず、翌週も眠そうにしてしまいました。
それ以来、休日でも7時台には起こすようにしたら、生活リズムが安定しました。
日中のお昼寝の取り方によっては、夜の寝つきが悪くなってしまうこともあります。
年齢別のお昼寝時間の目安や調整方法については、こちらの記事も参考にしてみてください。
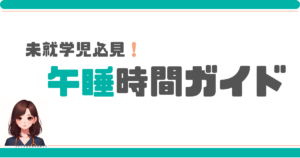
親ができるサポート|無理なく続ける関わり方
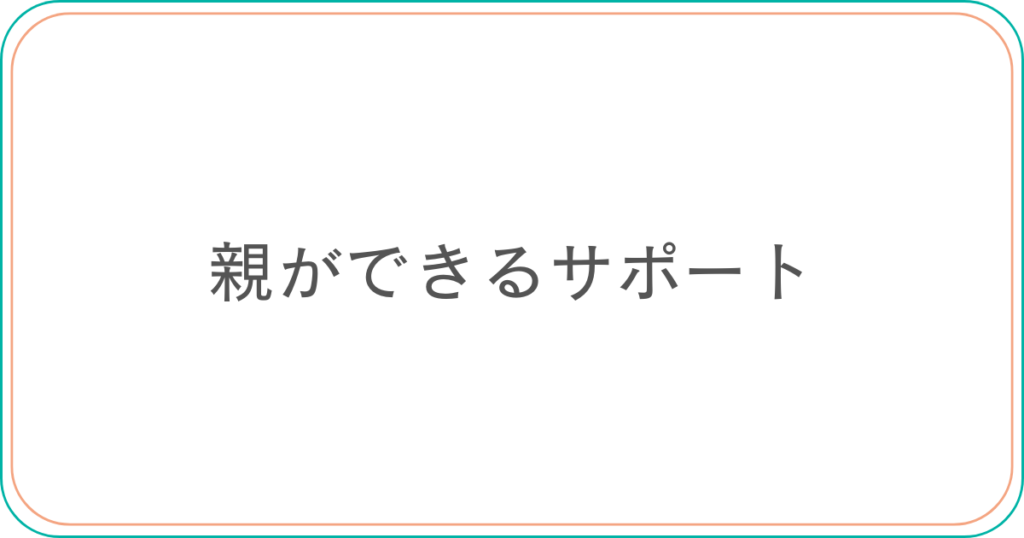
睡眠不足を改善するには、子ども自身に「早く寝なきゃ」と言い聞かせるだけでは難しいものです。
特に子どもにとっては、家庭での環境づくりや親の寄り添いが大きな支えになります。
1. 一緒に眠る・寄り添う
「早く寝なさい!」と頭ごなしに叱っても、かえって反発してしまい、布団に入る時間が遅くなってしまうこともあります。
それよりも 「一緒に布団に入ろう」「おやすみの前に少しお話ししよう」 と声をかけ、親も一緒に横になるほうが効果的です。
子どもにとって「親がそばにいてくれる安心感」は入眠を助ける大きな要素です。
特に秋休み明けのように生活リズムが乱れている時期は、数日間でも親子で同じ時間に布団に入る習慣をつくると整いやすくなります。
わが家では、秋休み明けの1週間だけ「寝る前に一緒に好きな本を読む→そのまま消灯」という流れを作りました。
すると自然に21時前には眠くなり、翌朝の機嫌も改善。
子ども自身が「朝が楽になった」と感じられるようになりました。
2. 食事時間を整える
食事は「体内時計」を整える大事なスイッチです。
特に朝ごはんは、体温を上げ、脳を活動モードに切り替える役割を持っています。
朝は 炭水化物(ご飯やパン)+たんぱく質(卵・魚・ヨーグルトなど) を意識してとると、エネルギー補給と血糖値の安定につながり、1日の集中力も高まります。
逆に夜遅い時間の食事やおやつは消化に時間がかかり、寝つきを妨げる原因になります。
就寝の2〜3時間前までに夕食を済ませるのが理想です。
「朝はパンだけで済ませがち」だったのですが、ヨーグルトやチーズをプラスするようにしました。
すると子どもが午前中に「お腹すいた」と言うことが減り、授業中の集中にもつながっているように感じます。
3. 学校・園との連携
子どもの生活リズムや睡眠の乱れは、家庭だけで気づけるとは限りません。
学校や園での様子を先生から教えてもらうことも大切です。
「午前中はぼーっとしている」などの情報は、家庭での生活を見直すきっかけになります。
また、家庭での状況(夜更かし気味、朝の寝起きがつらそうなど)を先生に伝えることで、学校でも配慮を受けやすくなります。
ある時、先生から「給食前に眠そうにしている」と言われたことがありました。
その日から寝る前の動画視聴をやめたところ、数日で改善。
家庭と学校が連携するとスムーズだと実感しました。
 まいこ@保育園看護師まま
まいこ@保育園看護師ままこのように、 親の寄り添い・食事の工夫・園との協力 により、秋休み後に乱れがちな生活リズムも整えやすくなります。
まとめ|秋休み後の睡眠不足は生活リズムの立て直しがカギ

- 秋休み後は生活リズムが乱れ、子どもの睡眠不足が増えやすい
- 睡眠不足は「集中力低下」「情緒不安定」「免疫力低下」「成長への影響」をもたらす
- 朝の光・就寝前の習慣・夕方の運動・休日の起床時間調整がリズム回復のカギ
- 保護者は「寄り添う姿勢」で子どもを支え、学校や園とも協力して見守ることが大切
秋休みを楽しく過ごすこと自体は悪いことではありません。
大切なのは「その後のリカバリー」。
少しずつ生活リズムを戻す工夫を取り入れることで、子どもは安心して学校生活へ戻っていくことができます。
 まいこ@保育園看護師まま
まいこ@保育園看護師まま秋休み後の睡眠不足は一時的なものが多く、起床時間を整え、日中の過ごし方を見直すことで、子どもの生活リズムは少しずつ安定していきます。

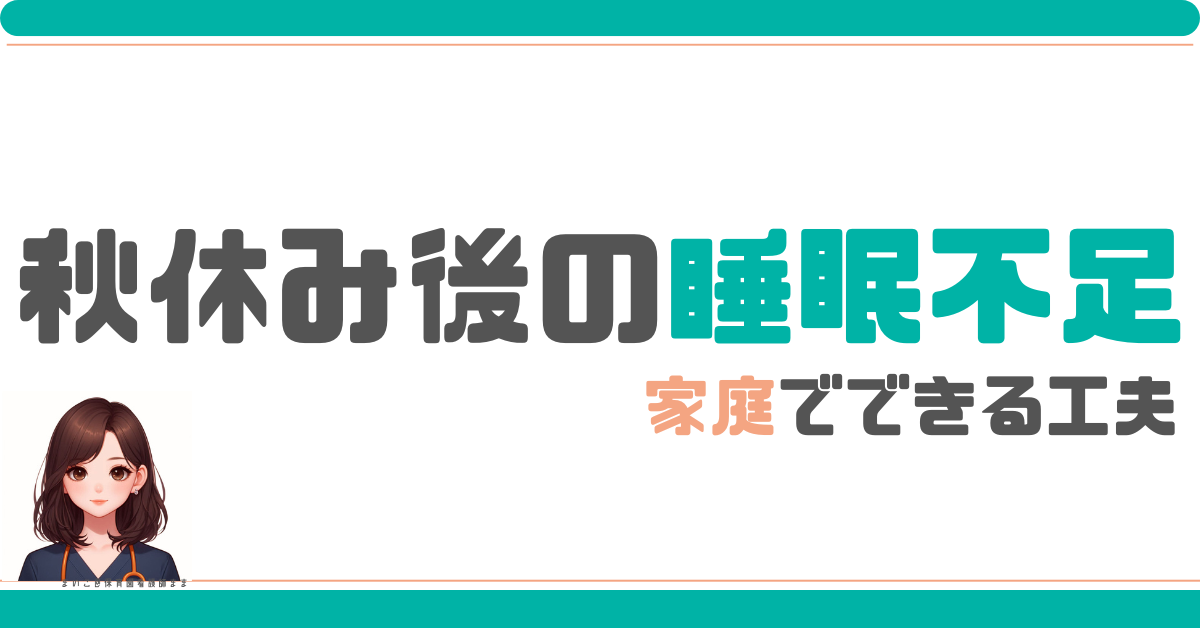
コメント