
子どもの胃腸風邪(感染性胃腸炎)は、突然の嘔吐や下痢、発熱を伴うことが多く、保護者にとって不安の大きい病気のひとつです。
「様子を見ていいの?」「受診のタイミングは?」「家族にうつさないためには?」
こうした疑問を抱えながら、慌てて対応した経験がある方も多いのではないでしょうか。
特に乳幼児や小さな子どもは脱水になりやすく、正しい対処を知っているかどうかで回復の早さや重症化リスクが大きく変わります。
この記事では、
子どもの胃腸風邪の原因・家庭でできる予防法・症状が出たときの正しい対応・受診の目安までを、保育園看護師の視点も交えながら、わかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 子どもの胃腸風邪(感染性胃腸炎)の原因や感染しやすい時期
- 嘔吐・下痢・発熱など、子どもに現れやすい症状の特徴と経過
- 胃腸風邪にかかったとき、家庭でできる正しい対処法
- 脱水を防ぐための水分補給のポイントと注意点
- 家庭やきょうだいへの感染を防ぐ予防対策
- 病院を受診したほうがよい症状と受診の目安
子どもの胃腸風邪(感染性胃腸炎)とは
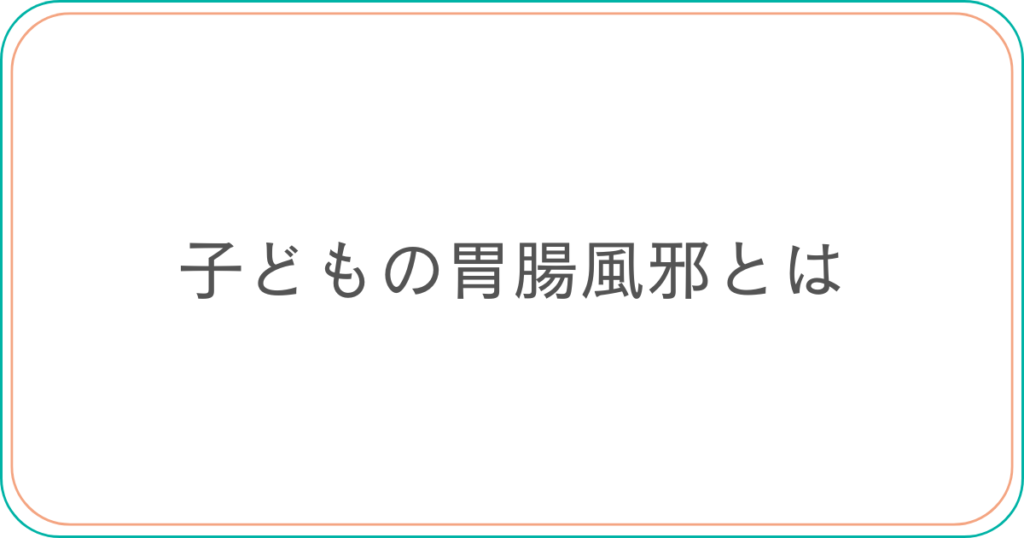
子どもの胃腸風邪は、正式には感染性胃腸炎と呼ばれ、ウイルスや細菌が原因で起こる病気です。
突然の嘔吐や下痢、発熱を伴うことが多く、特に乳幼児では症状が急に強く出ることもあります。
保育園や幼稚園などの集団生活では感染が広がりやすく、毎年冬を中心に多くの子どもがかかります。
子どもの胃腸風邪の主な原因
子どもの胃腸風邪の多くは、以下のようなウイルス感染が原因です。
- ノロウイルス
- ロタウイルス
- アデノウイルス
- サポウイルス など
これらは、
- 手や口を介した接触感染
- 吐物や便に含まれるウイルスによる感染
で広がります。特に、手洗いが不十分な乳幼児は感染しやすい傾向があります。
感染しやすい時期と年齢
胃腸風邪は秋〜冬に流行しやすい病気ですが、年間を通して発症する可能性があります。
- 乳児〜未就学児は重症化しやすい
- 小学生以降は比較的軽症で済むことも多い
ただし、年齢に関わらず脱水症状には注意が必要です。
胃腸風邪は主に秋〜冬に流行しやすい病気ですが、原因となるウイルスによって症状の経過には違いがあります。
【ウイルスごとの症状期間の目安】
・ノロウイルス:嘔吐や下痢が1〜2日程度で落ち着くことが多い
・ロタウイルス:下痢が1週間近く続く場合もあります
いずれの場合も、症状が強い間は脱水に注意し、無理をせず回復を優先しましょう。
子どもの胃腸風邪の主な症状
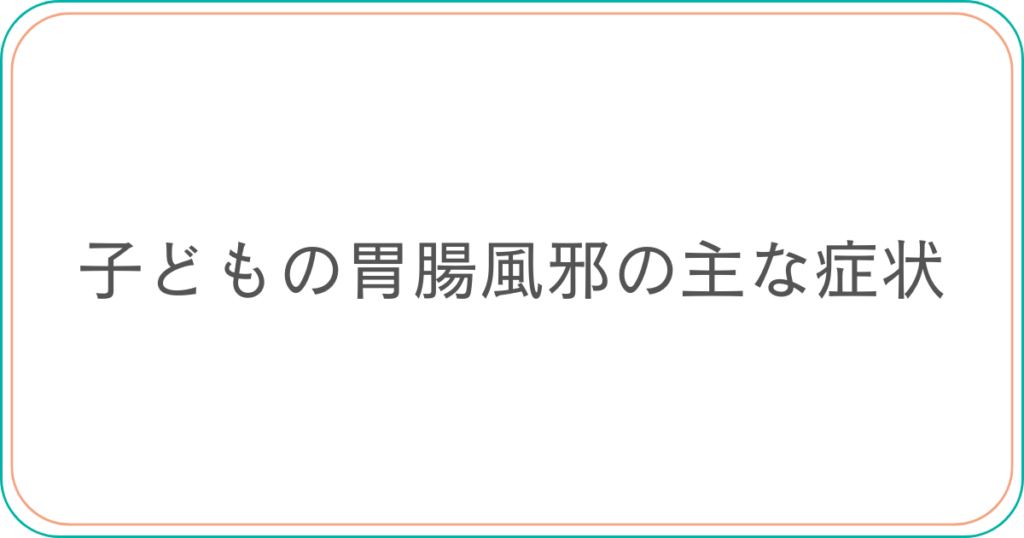
症状の出方には個人差がありますが、次のような症状がよく見られます。
嘔吐・下痢の特徴
- 突然何度も吐く
- 水のような下痢が続く
- 食事を受け付けなくなる
嘔吐は発症初日に集中することが多く、下痢は数日続くケースが一般的です。
発熱や腹痛を伴うこともある
- 38℃前後の発熱
- お腹の痛みを訴える
- 不機嫌・元気がない
これらの症状が同時に出ると、子どもも親も不安になりがちですが、多くは数日で回復します。
症状が続く期間の目安
- 嘔吐:1〜2日
- 下痢:3〜5日
- 食欲不振:回復後もしばらく続くことあり
ただし、水分が取れない状態が続く場合は要注意です。
家庭でできる正しい対処法
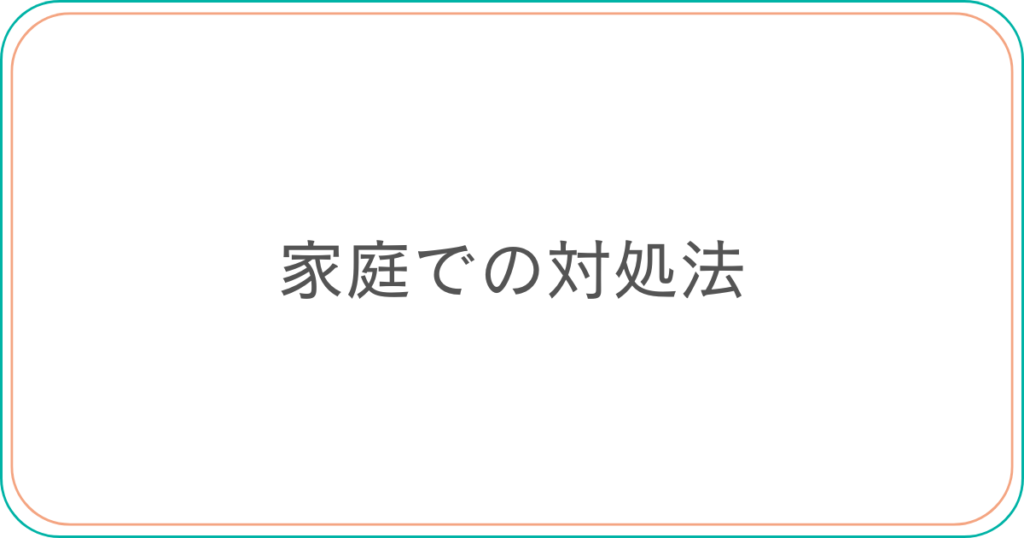
胃腸風邪にかかったときは、無理に食べさせない・水分補給を最優先にすることが大切です。
嘔吐があるときの対応ポイント
- 吐いた直後は無理に飲ませない
- 30分〜1時間ほど様子を見る
- 少量ずつ、スプーン1杯から再開
一気に飲ませると再度吐いてしまうことがあるため、**「少しずつ・こまめに」**が基本です。
下痢が続くときのケア
- お尻かぶれ予防のため、こまめに清拭
- 食事は消化の良いものから再開
- 脂っこい食事・乳製品は控える
下痢が続いても、元気があり水分が取れていれば慌てる必要はありません。
脱水を防ぐ水分補給のコツ
- 経口補水液(OS-1など)
- 湯冷まし・薄めた麦茶
- 氷をなめさせるのも有効
おしっこの回数や量が減っていないかを必ず確認しましょう。
多くの場合、子どもの胃腸風邪は家庭でのケアで回復しますが、症状や年齢によっては早めの受診が必要なケースもあります。
特に、水分が取れない・ぐったりしているなどの様子が見られる場合は注意が必要です。
病院を受診する目安については、こちらの記事で詳しく解説しています。
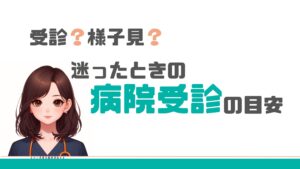
子どもの胃腸風邪を予防するためにできること
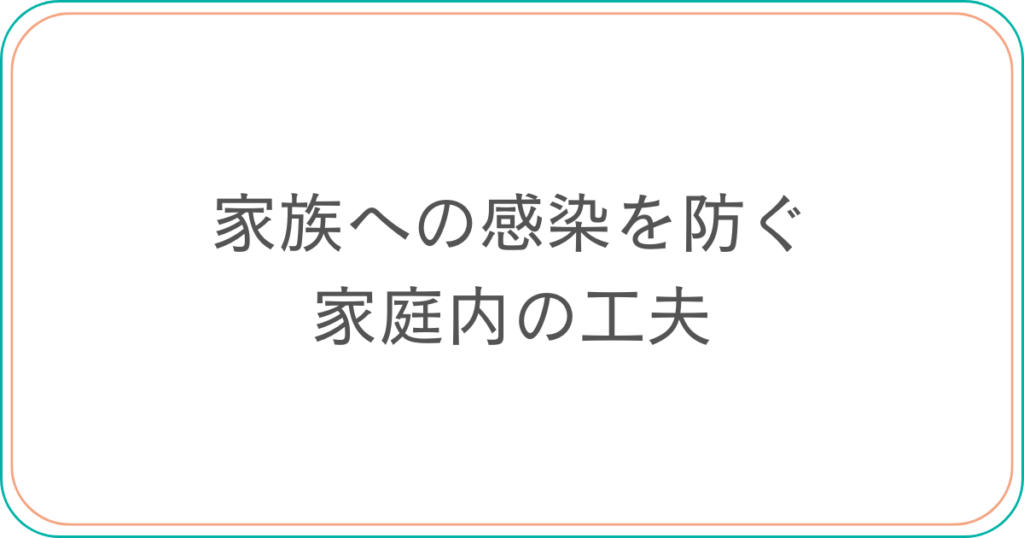
完全に防ぐことは難しいですが、日常生活でできる対策はあります。
家庭でできる感染対策
- 石けんを使ったこまめな手洗い
- タオルの共用を避ける
- トイレやドアノブの消毒
アルコールが効きにくいウイルスもあるため、次亜塩素酸系消毒が有効な場面もあります。
きょうだい・家族への感染を防ぐ工夫
- 吐物・便の処理は手袋着用
- 処理後はしっかり手洗い
- 可能であれば入浴・トイレの時間を分ける
家庭内感染を防ぐことで、看病する側の負担も軽減できます。
病院を受診したほうがよい症状の目安
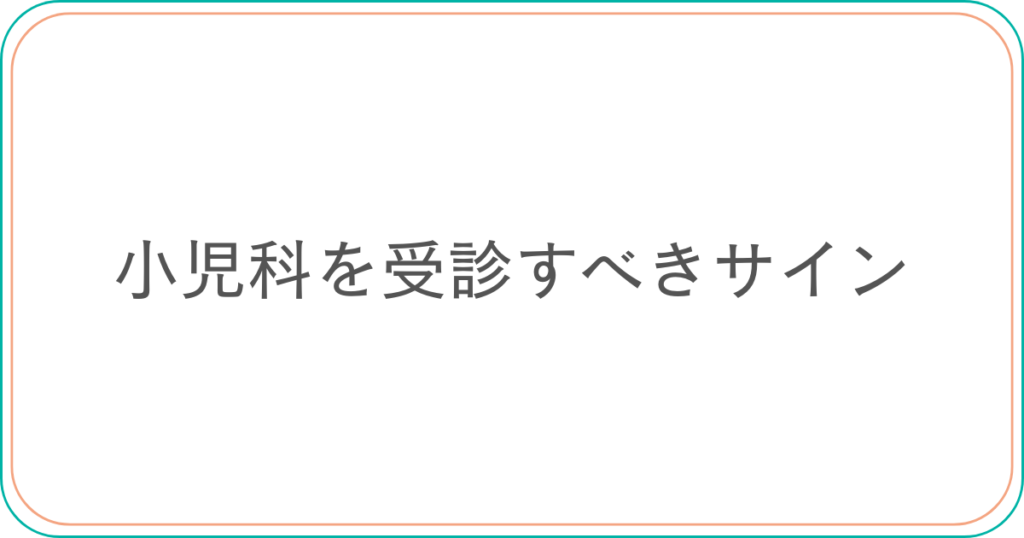
以下のような症状がある場合は、早めの受診を検討しましょう。
すぐ受診したほうがよい症状
- 水分をほとんど取れない
- 嘔吐が止まらない
- 半日以上おしっこが出ていない
- ぐったりして反応が鈍い
- 血便が出ている
様子を見てもよいケース
- 水分が取れている
- 元気があり遊べている
- 嘔吐や下痢が徐々に減っている
夜間・休日に迷ったときの考え方
「いつもと違う」「何かおかしい」と感じたら、迷わず医療機関や相談窓口を利用しましょう。
保護者の直感は大切なサインです。
よくある質問(Q&A)
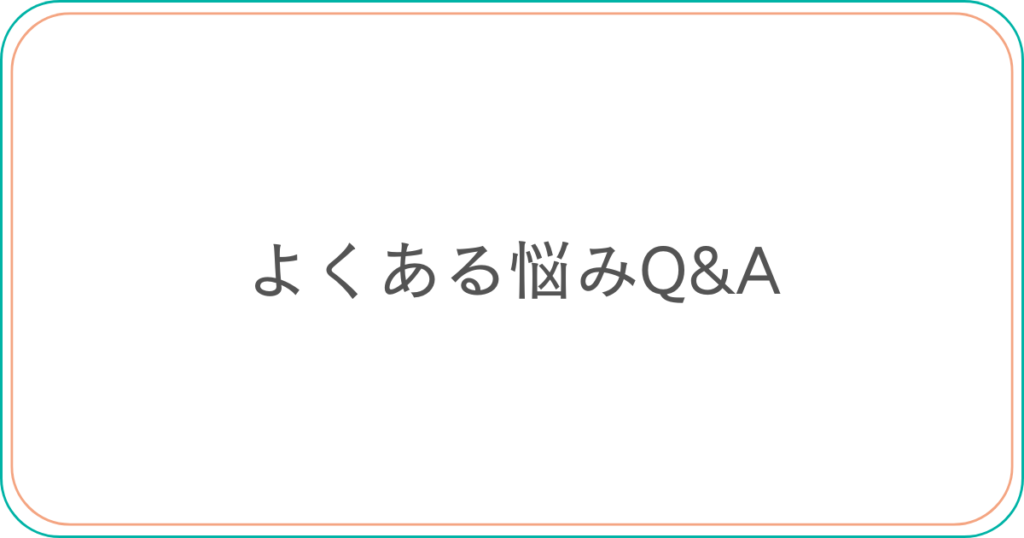
- 子どもの胃腸風邪はどれくらいで治りますか?
-
個人差はありますが、一般的には嘔吐は1〜2日、下痢は3〜5日程度で落ち着くことが多いです。
ただし、回復後もしばらく食欲が戻らないことがあります。
 まいこ@保育園看護師まま
まいこ@保育園看護師まま水分が取れていて元気がある場合は様子を見ても問題ありませんが、症状が長引く・悪化する場合は受診を検討しましょう。
- 胃腸風邪のとき、お風呂に入っても大丈夫ですか?
-
熱が高くなく、元気がある場合は短時間であれば入浴しても問題ありません。
ただし、嘔吐や下痢が続いているときは、体力を消耗しやすいため無理をしないことが大切です。
 まいこ@保育園看護師まま
まいこ@保育園看護師ままシャワーで軽く済ませる、体を拭くだけにするなど、子どもの状態に合わせて調整しましょう。
- 胃腸風邪のとき、食事はいつから再開すればいいですか?
-
嘔吐が落ち着き、水分が取れるようになってから少量ずつ再開しましょう。
最初は、
- おかゆ
- うどん
- すりおろしりんご
など、消化の良いものがおすすめです。
食欲がないときは無理に食べさせず、水分補給を優先してください。
- 胃腸風邪の後、保育園・学校はいつから行っていいですか?
-
嘔吐や下痢が治まり、普段通りの食事が摂れるようになり、体調が安定してからが登園・登校の目安です。
目安としては、最後の嘔吐や下痢から24時間以上経過していることを確認しましょう。
 まいこ@保育園看護師まま
まいこ@保育園看護師まままだ食欲が戻らない、下痢が続いている、元気がない場合は、無理をせずもう1日様子を見ると安心です。
また、園や学校によって登園・登校の基準が異なることがあるため、事前に確認しておくと安心です。
まとめ|子どもの胃腸風邪は正しい対処で落ち着いて対応を

子どもの胃腸風邪は、突然始まり不安になる病気ですが、
正しい知識と対応があれば、落ち着いて乗り越えることができます。
- 無理に食べさせない
- 水分補給を最優先
- 受診の目安を知っておく
 まいこ@保育園看護師まま
まいこ@保育園看護師まま日頃から備えておくことで、いざというときの安心につながります。

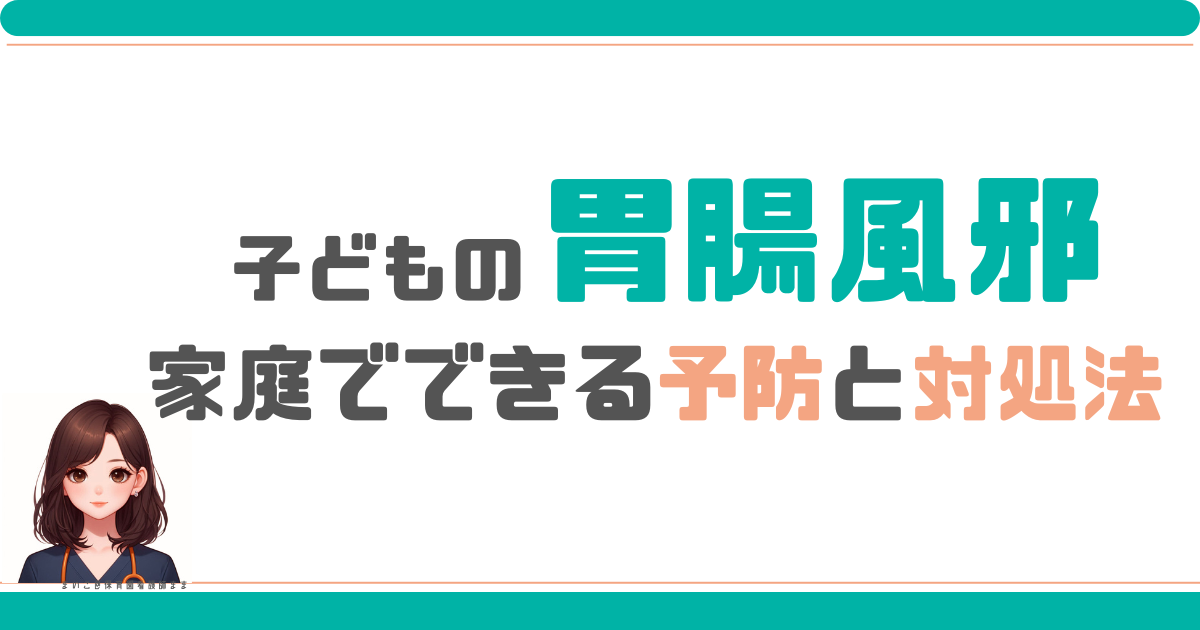
コメント