
未就学児のお昼寝(午睡)は、年齢や発達段階によって必要な時間や役割が大きく変わります。
「うちの子、もう昼寝しなくても大丈夫?」
「寝かせすぎて夜眠れなくならない?」
「保育園では寝ているのに、家では寝ない…」
そんな悩みを感じている保護者の方も多いのではないでしょうか。
お昼寝は、単なる休憩ではなく、脳の発達・情緒の安定・生活リズムを整える大切な役割があります。
この記事では、未就学児のお昼寝(午睡)について、年齢別の目安時間や必要性、家庭で生活リズムを整えるコツを、保育・医療の視点からわかりやすく解説します。
 まいこ@保育園看護師まま
まいこ@保育園看護師まま最後には体験談も紹介するので、日々の子育ての参考にしてみてください。
この記事でわかること
- 未就学児にお昼寝(午睡)が必要な理由
- 年齢別(0〜6歳)のお昼寝時間の目安
- 昼寝をしない・短いときの考え方
- 夜の睡眠に影響させない生活リズムの整え方
- 午睡中に親が気をつけたい安全面のポイント
未就学児にお昼寝(午睡)は必要?|役割と重要性
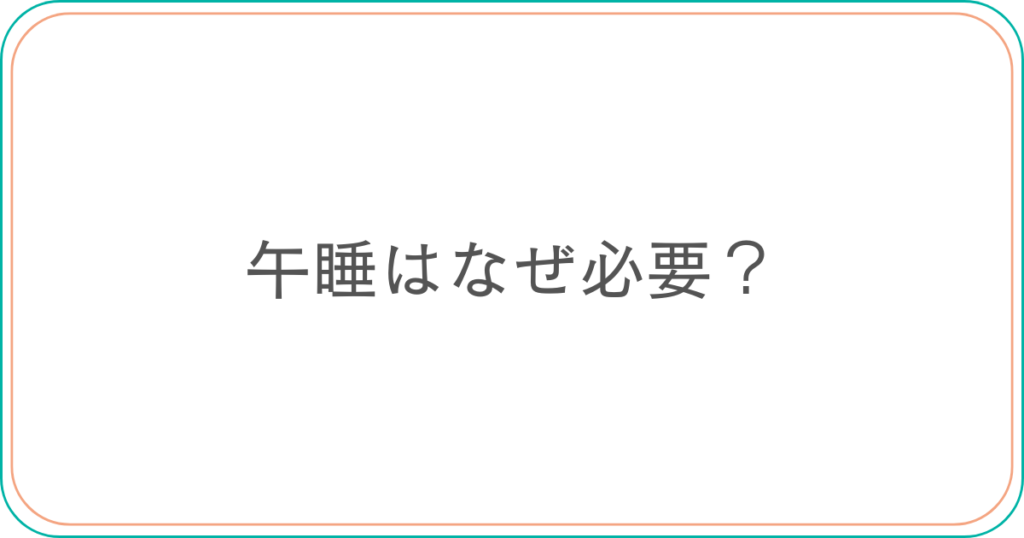
午睡は単なる「お昼の休憩」ではなく、子どもの発達に欠かせない役割を担っています。
特に未就学児の時期は心身の成長が著しく、質の良い休息がそのまま健やかな発達につながります。
1. 脳の発達をサポート
乳幼児期の脳は、大人以上のスピードで新しい情報を吸収しています。
言葉、体の動き、友達との関わり……毎日が学びの連続です。
- 睡眠中には記憶の整理や定着が行われるため、午前中に体験したことが午後の休息で脳に刻まれる
- 午睡をとる子どもは、集中力や学習能力が高まりやすいという研究報告も
 まいこ@保育園看護師まま
まいこ@保育園看護師まま午睡は「学んだことを定着させる時間」と考えるとわかりやすいです。
2. 成長ホルモンの分泌
子どもの体の発育に欠かせない成長ホルモンは、夜だけでなく日中の睡眠でも分泌されます。
- 成長ホルモンは骨や筋肉を育てるだけでなく、免疫機能や代謝にも関与
- 疲労回復や細胞修復の役割もあるため、午睡でしっかり休むことは病気に負けない体づくりにつながる
 まいこ@保育園看護師まま
まいこ@保育園看護師まま活発に動き回る年齢だからこそ「休む=成長する」時間が必要です。
3. 情緒の安定
午睡をとった日は午後もごきげんに遊べるのに、足りない日は夕方にぐずぐず……そんな経験はありませんか?
- 午睡不足は不機嫌・癇癪・集中力低下につながりやすく、ストレスとなる
- 午睡で一度リセットすると、午後の活動がスムーズになり、夜の入眠も楽になることが多い
 まいこ@保育園看護師まま
まいこ@保育園看護師まま午睡は「午後を気持ちよく過ごすためのリフレッシュ時間」と言えます。
午睡は、
- 脳の発達(記憶の整理・学びの定着)
- 体の発育(成長ホルモンの分泌・免疫強化)
- 心の安定(気分のリセット・機嫌改善)
この3つを同時にサポートしてくれる、子どもにとってとても大切な習慣です。
ただし、年齢が上がるにつれて必要な時間は変化していくため、「何時間寝かすか」ではなく「子どもの成長やリズムに合った休息をとれているか」がポイントになります。
【年齢別】未就学児のお昼寝(午睡)時間の目安
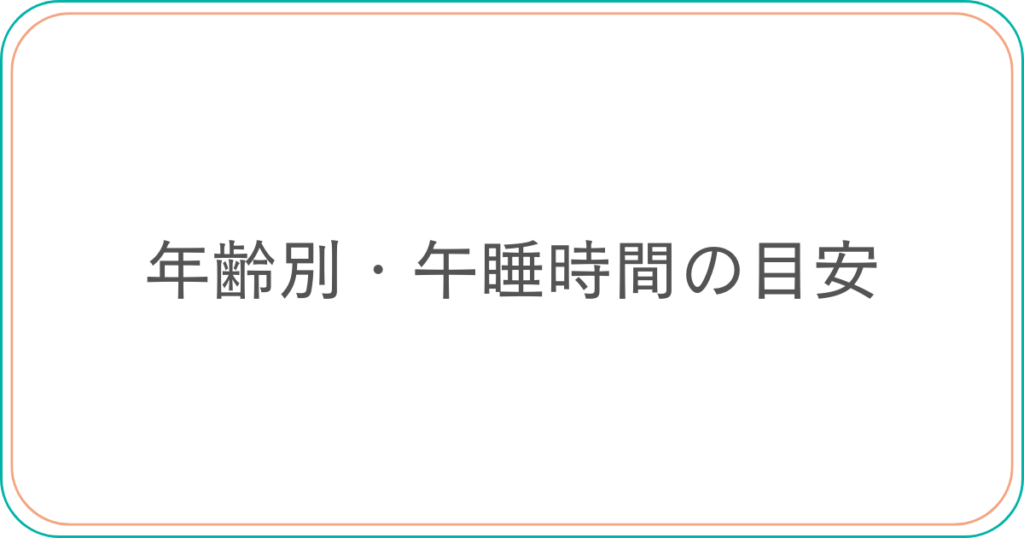
0〜1歳|お昼寝回数と合計睡眠時間の目安
0〜1歳の乳児期は、脳や身体の成長が非常に著しい時期であり、こまめなお昼寝(午睡)が欠かせません。
この時期の睡眠は「夜まとめて寝る」というよりも、1日の中で何度も眠るリズムが基本になります。
月齢によって個人差はありますが、目安としては以下のようなイメージです。
- 0〜3か月頃:昼夜の区別がまだなく、1〜2時間おきに眠る
- 4〜6か月頃:昼寝は1日3〜4回程度に落ち着いてくる
- 7〜12か月頃:午前・午後の2回昼寝が定着してくる
合計睡眠時間は、1日13〜15時間前後が目安とされています。
ただし、途中で目を覚ましたり、短時間睡眠を繰り返すことも多く、「ぐっすり長く眠らない=異常」というわけではありません。
大切なのは回数や時間にこだわりすぎず、機嫌よく起きて過ごせているか、授乳や離乳食が進んでいるかといった全体の様子を見ることです。
2〜3歳|昼寝はいつまで必要?
2〜3歳頃になると、体力がつき、活動量も一気に増えてきます。
その一方で、まだ自分で疲れを調整することが難しい時期でもあるため、昼寝は引き続き重要な役割を持ちます。
この年齢のお昼寝の目安は、
- 1日1回
- 1〜2時間程度
が一般的です。
ただし、成長とともに昼寝の時間が短くなったり、日によって眠らないことも出てきます。
「毎日必ず寝かせなければいけない」というよりも、午前中の活動量や午後の様子に応じて調整することがポイントです。
また、昼寝の時間が長すぎたり、夕方遅くまで寝てしまうと、夜なかなか寝つけなくなることもあります。
夜の睡眠に影響が出ている場合は、昼寝の終了時間を少し早めるなど、生活リズム全体を見直してみましょう。
4〜6歳(年中・年長)|昼寝しないけど大丈夫?
4〜6歳頃になると、昼寝をしなくても1日元気に過ごせる子が増えてきます。
特に年中・年長になると、家庭では昼寝をしなくなる一方で、保育園や幼稚園では午睡の時間が設けられていることもあり、戸惑う保護者の方も多いかもしれません。
この時期に昼寝をしないこと自体は、発達上、特に問題はありません。
重要なのは、
- 夜にしっかり眠れているか
- 日中、強い眠気や不機嫌さが目立たないか
といった点です。
もし昼寝をしない代わりに、夕方以降にぐったりしてしまう、集中力が続かないといった様子が見られる場合は、短時間の休息(横になる・静かに過ごす)を取り入れるだけでも十分なことがあります。
「昼寝をする・しない」よりも、子ども自身の生活リズムと体調に合っているかを基準に考えることが大切です。
| 年齢 | 午睡の回数 | 午睡時間の目安 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 0歳(新生児〜1歳) | 3〜4回 | 1回30分〜2時間、合計4〜5時間 | 昼夜の区別がまだはっきりせず、こまめに眠る |
| 1〜2歳 | 1〜2回 | 1〜2時間×1〜2回 | 活動が増えるが、まだまとまった午睡が必要 |
| 3歳 | 1回 | 1〜2時間 | 午後の1回が中心、保育園でも全員が午睡する年齢 |
| 4歳 | 0〜1回 | 30分〜1時間(必要に応じて) | 午睡なしで過ごせる子も増える |
| 5〜6歳 | ほとんどなし | 0〜30分程度 | 就学に向けて午睡は減少、夜の睡眠が中心に |
 まいこ@保育園看護師まま
まいこ@保育園看護師まま重要なのは「午睡だけでなく、夜の睡眠を含めたトータルで考えること」です。
昼寝をしない・短いときの考え方
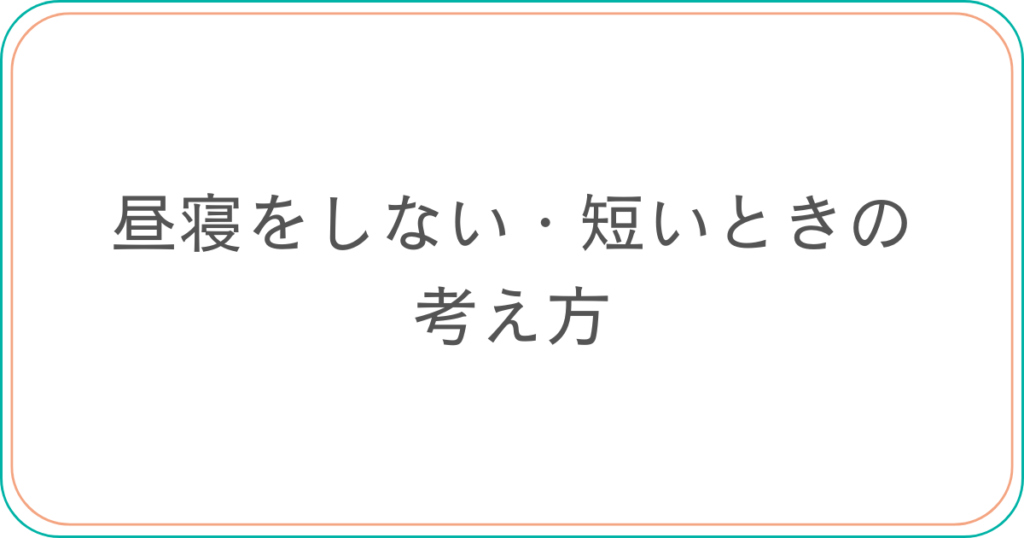
「昼寝をしない日が増えてきたけれど、大丈夫?」
「保育園では寝ているのに、家では全然寝ない…」
未就学児の昼寝に関する悩みは、とても多く聞かれます。
しかし、昼寝をしない=発達に問題がある、というわけではありません。
成長とともに体力や睡眠リズムは変化し、昼寝が必要な子もいれば、あまり必要としない子もいます。
まずは「なぜ昼寝をしないのか」を冷静に見ていきましょう。
昼寝を嫌がる理由とは?
未就学児が昼寝を嫌がる背景には、いくつかの理由があります。
- 体力がつき、眠くなりにくくなっている
- 午前中の活動量が少なく、疲れが足りない
- 刺激が多く、興奮状態が続いている
- 寝る環境(明るさ・音・室温)が合っていない
特に4〜6歳頃になると、「遊びたい気持ち」が勝って眠気を我慢することも珍しくありません。
この場合、無理に寝かせようとすると、かえって親子ともにストレスになってしまいます。
無理に寝かせなくてもいいケース
次のような様子が見られる場合は、昼寝をしなくても大きな心配はいりません。
- 夜は比較的スムーズに眠れている
- 朝、機嫌よく起きられている
- 日中、強い眠気や不機嫌さが続かない
睡眠は「昼寝+夜の睡眠」の合計で考えることが大切です。
昼寝をしなくなった分、夜の睡眠時間が確保できていれば問題ないケースが多いといえます。
生活リズムを見直したいサイン
一方で、次のようなサインが見られる場合は、昼寝や生活リズムの調整を検討してみましょう。
- 夕方になると極端に機嫌が悪くなる
- 夕食中やお風呂でうとうとする
- 夜になると逆に目が冴えてしまう
このような場合は、「短時間の昼寝」や「静かに横になる時間」を取り入れるだけでも、夜の睡眠が安定しやすくなります。
夜の睡眠に影響させないための生活リズム調整法
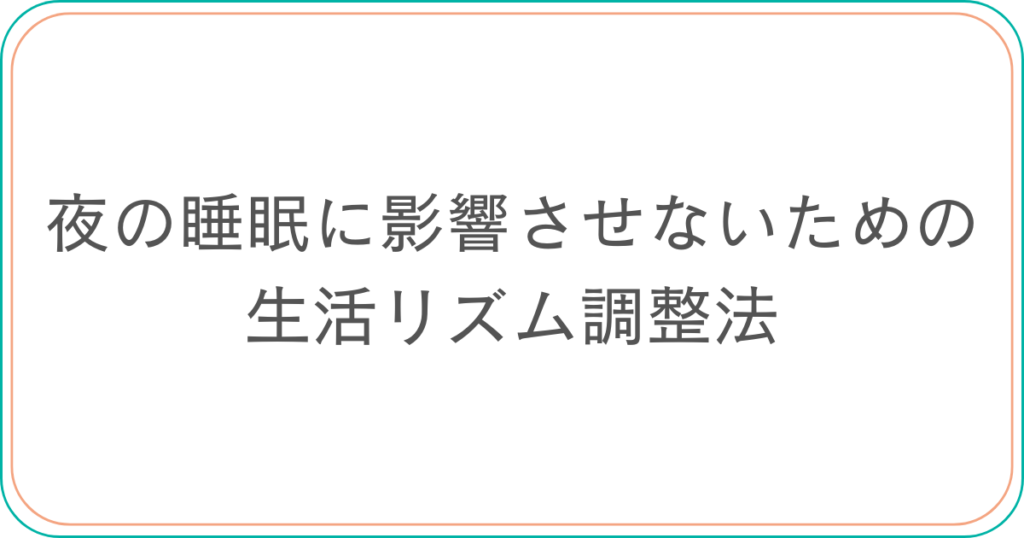
昼寝は、取り方を間違えると夜の睡眠に影響することがあります。
大切なのは、昼寝を“減らす・なくす”ことではなく、時間とリズムを整えることです。
お昼寝の終了時間の目安
未就学児のお昼寝は、遅くとも15時頃までに終えるのがひとつの目安です。
特に2〜3歳以降は、
- 昼寝が長すぎる
- 夕方近くまで寝てしまう
と、夜の寝つきが悪くなりやすくなります。
「寝る時間」よりも、起きる時間を意識することがポイントです。
起床時間・就寝時間を一定にするコツ
生活リズムを整えるうえで重要なのは、
毎日の起床時間と就寝時間を大きくずらさないことです。
- 朝はなるべく同じ時間に起きる
- 休日も寝坊しすぎない
- 夜は入浴・絵本・消灯の流れを固定する
こうした積み重ねが、昼寝の有無に関わらず、安定した睡眠リズムにつながります。
休日の過ごし方で気をつけたいこと
休日は生活リズムが乱れやすいものです。
外出やイベントがある日は、昼寝の時間がずれたり、取れなくなることもあるでしょう。
そんな日は、
- 早めに就寝する
- 夕方以降は静かな遊びに切り替える
など、夜の睡眠を優先する工夫がおすすめです。
無理に平日と同じ昼寝を取らせようとせず、1日単位ではなく、数日単位で整える意識を持つと、親の気持ちもラクになります。
未就学児のお昼寝中に気をつけたい安全面のポイント
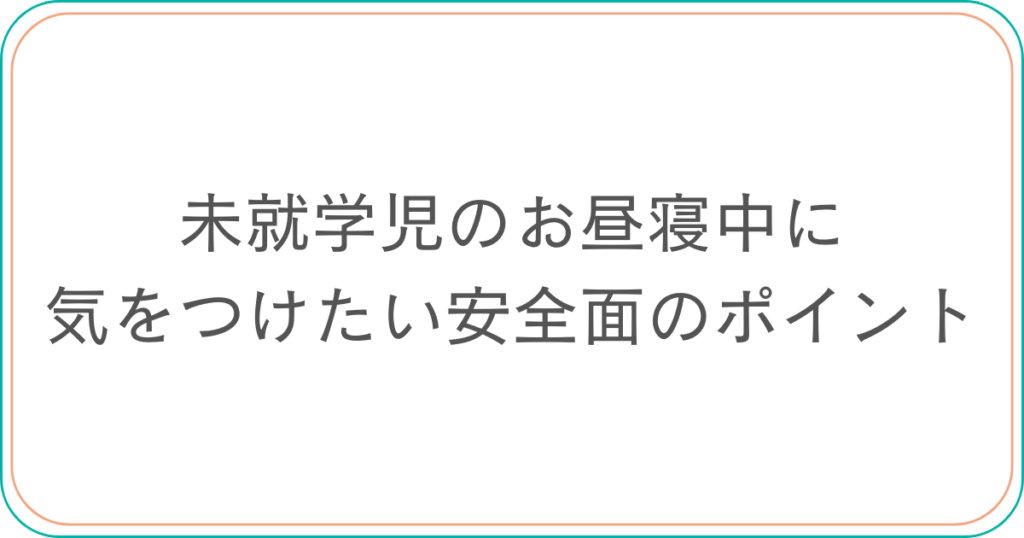
未就学児のお昼寝(午睡)は、心身の回復にとって大切な時間ですが、年齢が低いほど安全面への配慮が欠かせません。
特に家庭では、保育園のように複数の大人の目があるわけではないため、環境づくりと見守りの工夫が重要になります。
ここでは、未就学児のお昼寝中に保護者が意識しておきたい安全面のポイントを整理します。
月齢・年齢によって注意したいこと
お昼寝中の注意点は、子どもの年齢や発達段階によって異なります。
- 0〜1歳頃
寝返りやうつ伏せになる時期のため、窒息や呼吸の妨げに特に注意が必要です。
柔らかすぎる寝具や、顔の周りに物を置かないようにしましょう。 - 2〜3歳頃
寝相が悪くなり、布団からはみ出したり、顔にタオルがかかることがあります。
安全な範囲で寝られるよう、寝る場所の周囲を整えることが大切です。 - 4〜6歳頃
大きな事故のリスクは減りますが、体調不良や発熱時は注意が必要です。
いつもと様子が違う場合は、こまめな確認を心がけましょう。
室温・服装・寝具のチェックポイント
お昼寝中の事故や体調不良を防ぐためには、環境面の調整も重要です。
- 室温は夏は26〜28℃、冬は20〜22℃を目安にする
- 汗をかきやすい子は、吸湿性のよい服装を選ぶ
- 掛け布団は軽く、顔にかからないものを使う
- ベッドや布団の周囲に、コード類や小物を置かない
特に夏場は、知らないうちに体温が上がりやすいため、エアコンや扇風機を上手に使い、快適な睡眠環境を整えましょう。
見守りが不安なときの工夫
「お昼寝中、ずっとそばで見ていられない」
「家事をしている間も、ちゃんと眠れているか心配」
こうした不安を感じる保護者の方は少なくありません。
特に低年齢の未就学児の場合、目を離している時間の見守りが大きな課題になります。
そのようなときは、
「完全に目を離さない」ことを目指すのではなく、無理なく見守れる環境を整えることが大切です。
例えば、子どもの睡眠中の様子を把握できる見守り機器を活用することで、
家事をしながらでも安心してお昼寝時間を見守ることができます。
特に月齢の低い未就学児の場合、「ちゃんと呼吸できているかな」「うつ伏せになっていないかな」と、お昼寝中も気がかりになることがあります。
ずっとそばで見ているのが難しいときは、子どもの呼吸や睡眠の様子を見守れる機器を活用するのも一つの方法です。
実際にわが家でも使用している【ベビーセンスベビーモニター】は、赤ちゃんの呼吸の動きを感知し、異常があればアラームで知らせてくれるため、お昼寝中や家事をしている間も安心感につながりました。

すべての家庭に必須というわけではありませんが、不安が強い時期の「安心材料」として取り入れる家庭も増えています。
保護者の「安心」が子どもの安心につながる
お昼寝中の安全対策は、「何か起きないようにする」だけでなく、
保護者自身の不安を軽くすることも大切な目的のひとつです。
親が安心して過ごせることで、子どもも落ち着いて眠りやすくなります。
完璧を目指すのではなく、できる範囲で環境と見守りを整えることを意識してみてください。
まとめ|未就学児のお昼寝は年齢と生活リズムがカギ

未就学児のお昼寝(午睡)は、年齢や発達段階によって必要性や時間が大きく異なります。
「何歳まで昼寝が必要か」「しない日は問題ないのか」と悩む場面も多いですが、一律の正解はありません。
大切なのは、
- 年齢ごとの発達に合っているか
- 夜の睡眠を含めた生活リズムが整っているか
- 日中、機嫌よく元気に過ごせているか
といった子ども自身の様子を見ることです。
昼寝をしない日があっても、夜にしっかり眠れていれば問題ないケースは多くあります。
一方で、夕方以降の疲れや不機嫌さが目立つ場合は、昼寝の時間や取り方を見直すサインかもしれません。
また、年齢の低い未就学児では、お昼寝中の安全面への配慮も欠かせません。
無理のない見守り環境を整えることで、保護者の不安が軽減され、子どもも安心して眠ることができます。
 まいこ@保育園看護師まま
まいこ@保育園看護師まま「昼寝をさせる・させない」にとらわれすぎず、その子に合った睡眠リズムを、家庭の生活に合わせて整えていくことが何より大切です。

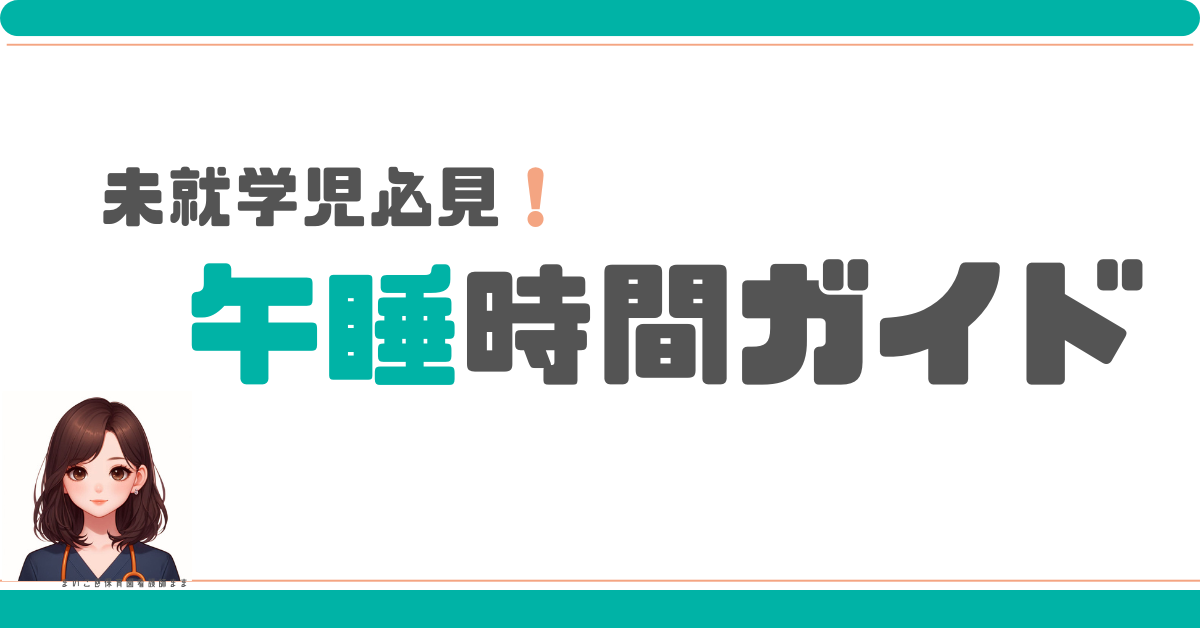
コメント